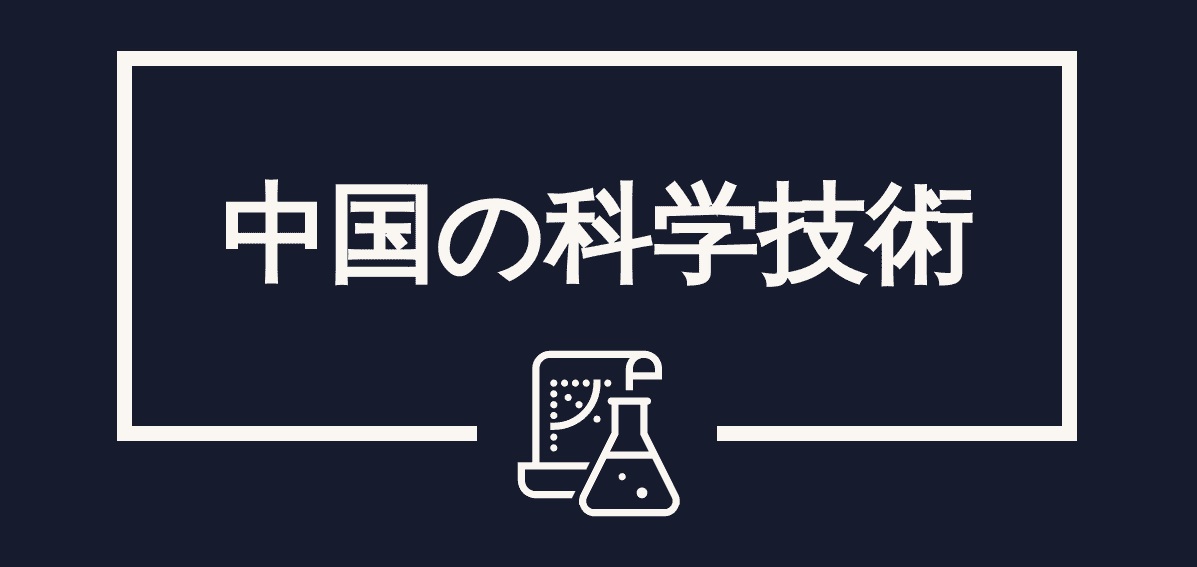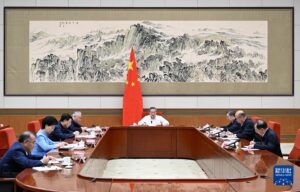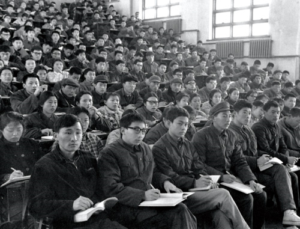Deng-Xiaoping Era
1. 鄧小平時代の歴史的な流れ
(1)文革からの回復と改革開放政策
1976年12月、中国共産党中央委員会は、「四人組に反対して迫害を受けた全ての人々の名誉の一律回復」を通達した。
華国鋒は文革時代に低迷を続けた経済の再建に取り組んだが、当時の中国経済の現実に立脚しておらず、順調には進まなかった。

鄧小平は、華国鋒との路線闘争を経て、1978年12月の中国共産党第11期三中全会で政治的なイニシアティブを確立した。鄧小平は最高指導者として、日本視察や米国視察を経て、革命路線から近代化路線へ大衆的な階級闘争から改革開放路線への転換を進めた。
農村改革では、「家庭請負責任生産制」を各地に拡大し、人民公社を解体した。農業の多角化、郷鎮企業の勃興の基盤となった。
都市部では外資の積極利用が奨励され、1980年に深圳、珠海、厦門、汕東の4地区に経済特区が、1984年に上海、天津、広州、大連などの沿岸部諸都市に経済技術開発区が設置された。
(2)党内対立の顕在化と経済改革の行き詰まり
1985年ころから改革開放に伴う問題や矛盾が顕在化してきた。役人ブローカー(官倒)や彼らの特別な関係者らは、安価な価格で手に入れた大量の物品を市場に横流しして莫大な利益を得た。彼らの腐敗・汚職が社会的に拡大し、市場では市民たちが急激な物価上昇に翻弄されるなど、社会混乱が目立ってきた。
このため、市場化をいっそう強めようとする鄧小平・趙紫陽ら改革派と、社会主義計画経済を維持すべきとする陳雲ら保守派との対立が顕在化してきた。
最も積極的な改革推唱者は胡耀邦総書記で、経済の民主化のためにこそ政治の民主化が必要であるとの主張が一定の支持を得るようになった。しかし、政治改革論議は「党の指導」に抵触することになり、政治混乱を引き起こした。

1987年1月、前年末に全国で高まった民主化要求の学生運動に同情的で軟弱な態度をとったなどの理由で胡耀邦が失脚した。改革派の後退かとみられたが、鄧小平は後継の総書記に趙紫陽を指名し、改革開放の推進を内外にアピールした。
(3)天安門事件と南巡講話
1989年には天安門事件が発生したが、鄧小平は中国共産党の指導性を揺るがす動きには厳しい態度で臨み、同年6月には学生運動の武力弾圧に踏み切った。鄧小平は、武力弾圧に反対した趙紫陽総書記の解任を決定するとともに、武力弾圧に理解を示し上海における学生デモを無難に処理して評価された江沢民(当時上海市党委書記)を、中国共産党総書記へ抜擢した。
天安門事件での武力行使は国際社会に大きな衝撃を与え、各国は経済交流などを中断した。同年11月、ベルリンの壁が崩壊し、東西冷戦が終結を迎えた。東欧やソ連の社会主義体制の危機を前にして舵取りが困難な情勢にあって、中国共産党内では李鵬などの保守派が台頭し、さらなる思想引き締めを主張した。一方、党内の改革派は、改革推進と経済発展が社会の安定と人民の支持を得る道であると主張し、路線対立が激化した。

鄧小平は、1992年春節の頃に深圳や上海などを視察して南巡講話を発表し、経済発展の重要性を主張するとともに、ペレストロイカによるソ連の解体などを例にとって党内保守派を厳しく批判した。この南巡講話により、天安門事件後に起きた党内の路線対立は収束し、改革開放路線を維持・推進するのに決定的な役割を果たした。
2. 鄧小平時代の科学技術の特徴
鄧小平時代の科学技術政策は、文革の破壊と混乱を立て直すことが第一であった。鄧小平は、科学技術を重視し、様々な政策を推し進めた。
(1)文革時代の負の遺産からの脱却
鄧小平時代の科学技術の特徴の一つ目は、文革時代の負の遺産からの脱却である。
四人組逮捕直後の1976年12月に、「四人組に反対して迫害を受けた全ての人々の名誉の一律回復」が通達され、でっち上げ・誤審が覆されて冤罪が晴らされた多数の科学者・研究者が教壇や科学研究に戻った。
中国科学院に併合されていた国家科学技術委員会は、分離独立して業務を再開した。中国科学院では地方に移管された研究機関が再び戻り、また数多くの新しい科学研究機関が設立された。文革中にほとんど活動を停止していた大学などの平常業務への復帰が急ピッチで進んだ。
文革開始直後に停止された高考の復活も重要である。鄧小平は、復活直後の1977年8月に中国科学院、中国農業科学院、北京大学、清華大学などの学者を招集して科学教育研究座談会を開催し、中断されていた高考の復活を速やかに実施することを宣言した。
このような文革の混乱からの脱却を歓迎して、郭沫若中国科学院院長は「科学の春(科学的春天)」というメッセージを発表して歓迎した。
(2)科学技術と経済の連携
鄧小平時代の科学技術の特徴の二つ目は、科学技術と経済の連携である。
鄧小平が常に強調したのは科学技術を含む四つの近代化であり、そのなかでも科学技術は第一の生産力として最も重視すべきということであった。四つの近代化は、元々周恩来が文革前から強調していたことであったが、鄧小平がこれを引き継ぎ、この言葉に魂を入れたのである。
四つの近代化と科学技術は第一の生産力というスローガンは、その後一貫して中国の科学技術政策の根幹をなす思想となり、四つの近代化は中国の憲法にも明記されることとなった。
鄧小平の科学技術に対する考えは、天安門事件やその後の西側諸国の経済制裁を経て生じた陳雲などの保守派との路線対立でも全く動じることがなく、南巡講話により次の世代に引き継がれていった。
(3)計画に基づく科学技術推進への回帰
鄧小平時代の科学技術の特徴の三つ目は、計画に基づく科学技術推進への回帰である。
1981年4月、中国共産党中央は改革開放路線をより明確にするため、科学技術に関わる中長期計画の策定を国務院に命じた。1982年末に国務院は、国家計画委員会と国家科学委員会が策定した「科学技術発展計画(1986年~2000年)」を承認した。
科学技術を計画的に推進するため、科学技術体制の改革も進められた。
1985年、中国共産党中央は「科学技術体制改革に関する決定」を発表し、科学技術活動の運営メカニズムを変え、科学技術体系の組織構造を調整し、科学技術人材の管理制度を見直すことを促した。
さらに1987年、国務院は「科学技術体制の深化にかかわる若干の問題の決定」を公表し、科学研究機関の自由化、科学研究者の管理政策の緩和、科学技術と経済の統合の推進に関して具体的な措置を提案した。
(4)西側諸国との国際交流の再開
鄧小平時代の科学技術の特徴の四つ目は、西側諸国との国際交流の再開である。
新中国建国後に東側陣営に属したため、科学技術の国際協力もソ連を中心とした東側諸国との交流が中心であったが、スターリン批判後に中ソ対立が生じソ連との協力が滞り、文革中を含めて閉鎖的な状況に置かれた。
転機となったのは、1972年のニクソン米国大統領訪中や田中角栄日本国首相訪中であったが、文革中は四人組のために交流は本格化しなかった。
鄧小平が実権を握ると大きく変化し、米国や日本などの西側諸国との交流が再開され、多くの有為な学生や研究者が米国、欧州、日本などに留学生として派遣された。
(5)プロジェクト資金や競争的資金の導入
鄧小平時代の科学技術の特徴の五つ目は、プロジェクト資金や競争的な資金の導入である。
文革前は、平等主義の徹底から国立の研究機関や大学では研究者数に応じて平等に研究費を配分することが中心であったが、これを国として重要なプロジェクトに重点配分するシステムに作り上げていった。
具体的には、1982年に「国家科学技術難関突破計画」が開始され、その後「星火計画」、「国家ハイテク研究発展計画(863計画)」、などが相次いで開始された。
さらに、米国などの例に倣い、研究者同士の競争を促して意欲のある優れた研究者に研究費を重点配分していく競争的資金制度を導入した。その一環で1986年に、米国科学財団(NSF)を模して国務院内の組織として国家自然科学基金委員会(NSFC)を設立した。
(6)地域科学技術の振興
鄧小平時代の科学技術の特徴の六つ目は、地域科学技術の振興である。
鄧小平は、地域の経済発展にも目を配り深圳などの地域を経済特区(1980年)、経済技術開発区(1984年)として発展を促した。その結果、軽工業などが中国の工業化を牽引することになったが、それまで国営企業が中心であったエネルギー、運輸、素材などの産業部門が低迷し産業の不均衡が生じた。
そこで1988年、経済の持続的な発展のため、大学や研究機関の成果によりこれら既存の産業のハイテク化を目指し、地方におけるハイテク産業活性化を目指す「国家ハイテク産業開発区」の設置、およびそれを支える「たいまつ計画」が開始された。これらの政策を受けて、中国のシリコンバレーを目指して「北京新技術産業開発区(中関村ハイテクパーク)暫定条例」が施行された。
この時代に始まった地域科学技術の振興は、現在においても地方科学技術庁や地方科学技術協会がその役割を担っており、それぞれの地方独自の活動を展開している。
3. 鄧小平時代の科学技術成果
この時期は文革の後遺症からの回復期であり、優れた研究者らは続々と米国などに赴いて研究にいそしみ力を蓄えた。
したがって、それほど大きな成果は見られないが、両弾一星政策の完成を受けて、これを民生に転化したことが重要である。原子力では、大型国産原子力発電所である秦山原子力発電所が浙江省嘉興市に1985年に建設が開始され、1991年12月に試運転を開始した。また東方紅一号衛星を打ち上げたロケットは、その後長征シリーズとして民生用に開発され、通信衛星や地球観測衛星、気象衛星の打ち上げが実施されていった。
スーパーコンピュータ開発でも成果が上がり、1983年国防科学技術大学が開発した「銀河」が毎秒一億回の計算速度を達成して、米国や日本に続いた。同大学はさらに1992年に「銀河2号」を完成させ、毎秒10億回の計算速度を達成した。
1988年には、中国科学院高エネルギー物理研究所が電子陽電子衝突加速器(BEPC)が運転を開始した。この加速器は、鄧小平が文革後に建設を承認し、米国のスタンフォード大学との協力の下に建設が進められたものである。
次表は改革開放直後と南巡講話後の科学論文数と世界順位を、米国や日本と比較したものである。文化大革命の影響を受けて1981年では世界24位と振るわず、米国の約80分の1、日本の14分の1に過ぎなかった。南巡講和後であっても14位で、米国の約20分の1,日本の約5分の1に過ぎず、この時期は次の時代の発展に向けての準備期間であった。
表 主要国の科学技術論文数の比較(単年、整数カウント法)
| 国名 | 1981年の論文数 | 順位 | 1992年の論文数 | 順位 |
| 中国 | 1,769 | 24 | 9,119 | 14 |
| 米国 | 139,757 | 1 | 191,913 | 1 |
| 日本 | 25,173 | 4 | 46,558 | 2 |
参考資料
・文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2019」
https://www.nistep.go.jp/archives/41356