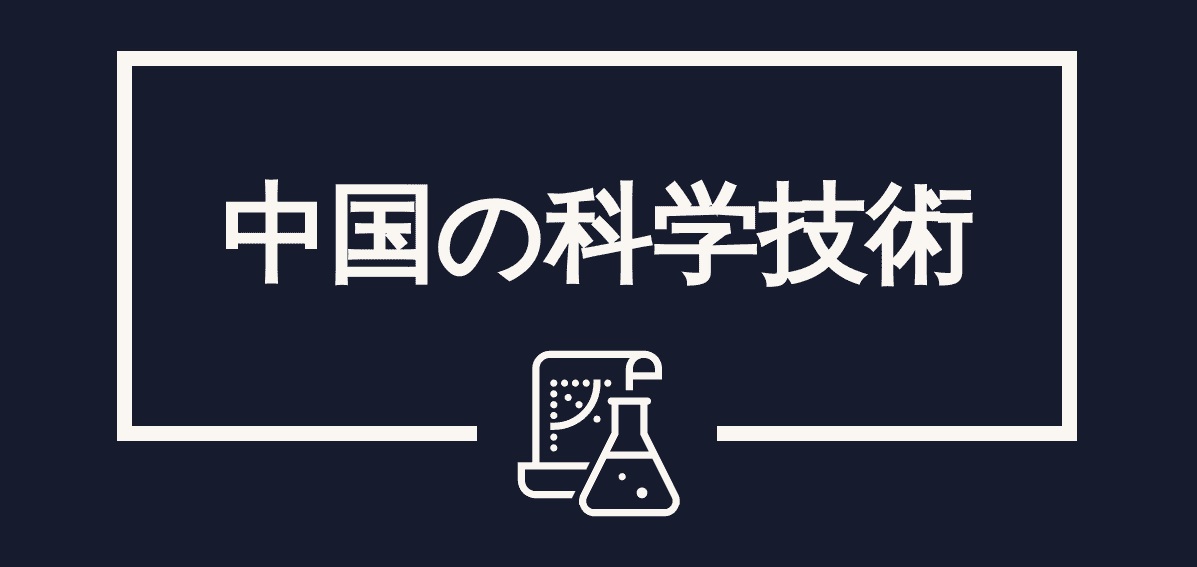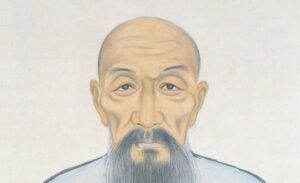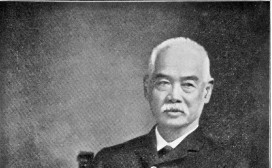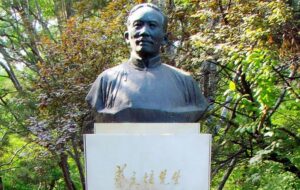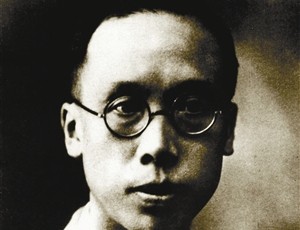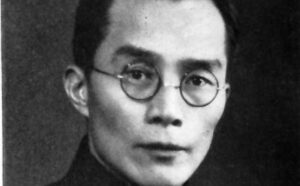Scientists & Leaders at the End of Qing Dynasty and Republic of China
中国において、西欧流の科学技術活動が本格化したのは、清朝がアヘン戦争で英国に敗北したのちのことである。その後、辛亥革命を経て清朝は滅亡し中華民国が建国したが、軍閥の台頭と日本や西欧列強の侵略があって政治的に混乱した。
そのような中でも、西欧や日本の軍事的な圧力を跳ね返すべく科学技術の振興への努力は続けられ、人材育成の面でも欧米に倣っての大学が設置された(清朝末期から国民政府の時代を参照されたい)。この時代に科学技術振興に重要な役割を果たした科学者や指導者を以下に取り上げる。
曾国藩(Guofan Zeng、1811年~1872年)
曾国藩(1811年~1872年)は、アヘン戦争やアロー戦争さらには太平天国の乱を経て、衰えつつある清朝を復活させるための改革であった洋務運動の主導者として、科学技術や高等教育の振興に最も尽力した。
李善蘭(Shanlan Li、1811年~1882年)
李善蘭(1811年~1882年)は、衰えつつある清朝を復活させるための改革であった洋務運動において、数学を中心とした研究や欧米の書籍の翻訳で画期的な成果を挙げ、北京大学の前身である京師同文館で教鞭を取った。
徐寿(Xu Shou、1818年~1884年)
徐寿は、清末の洋務運動を主導した曾国藩や翻訳家で数学者の李善蘭らと共に、蒸気船開発や近代化学の導入に尽力した。
容閎(Yung Wing、1828年~1912年)
容閎(1828年~1912年)は、清朝末期に米国に留学し、米国留学制度の先鞭となった幼童留美政策を推進した。中国の近代科学技術を支え育んだ人たちは、圧倒的に米国に留学した経験を有している。
詹天佑(Tianyou Zhan、1861年~1919年)
詹天佑(1861年~1919年)は、清朝末期に幼童留美政策により米国に留学し、帰国後中国の鉄道建設に尽力して「中国鉄道の父」と呼ばれた。
蔡元培(Yuanpei Cai、1868年~1940年)
蔡元培(1868年~1940年)は、中国の最高峰の大学である北京大学の基礎を築いた。中国の高等教育の歴史は、清朝末期から国民政府時代に始まっている。現在、北京大学や清華大学は世界のトップクラスに位置している。
鐘観光(Kuan Kwang Tsoong、1868年~1940年)
鐘観光(1868年~1940年)は、大学などの高等教育や外国への留学の経験がないが、清朝末から中華民国の時代に広大な中国で精力的に植物採集を行い、中国の近代植物学の礎を築いた。
伍連徳(Lien-teh Wu、1879年~1960年)
伍連徳(1879年~1960年)は、清朝末期に英国領マラヤに生まれ、満州で発生したペストと戦い、中国系で初めてノーベル賞候補に推薦された。
顔福慶(Fuqing Yan、1882年~1970年)
顔福慶(颜福庆)は、「南の湘雅、北の協和」と呼ばれる湖南省長沙の湘雅医学専門学校の設立に尽力し、初代の学長となった。
范旭東(Xudong Fan、1883年~1945年)
范旭東(范旭东)は、日本の京都帝国大学で工業化学を学び、国民政府の時代に製塩やアルカリ製造の事業を中国で興した実業家である。
梅貽琦(Yi-chi Mei、1889年~1962年)
梅貽琦(1889年~1962年)は、北京大学と並び称される名門大学である清華大学の基礎を築き、台湾に渡った後も国立清華大学の創設に尽力し初代学長となった。
参考資料
・JST中国総合研究・さくらサイエンスセンター『中国の科学技術の政策変遷と発展経緯(PDF)』2019年
・天児慧『中華人民共和国史』岩波新書 2013年
・天児慧『中国の歴史11 巨龍の胎動』講談社 2004年
・安藤正士『現代中国年表1941-2008』岩波書店 2010年