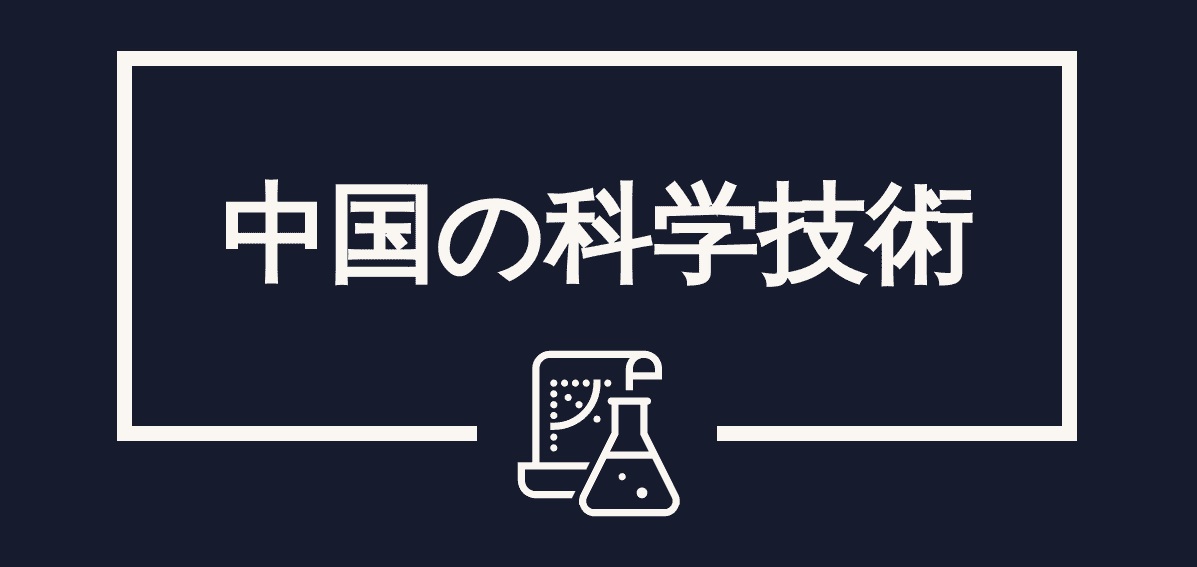はじめに
上海珪酸塩研究所(上海硅酸盐研究所、Shanghai Institute of Ceramics)は、上海市にある中国科学院の附属研究機関である。
高性能構造セラミックス、機能性セラミックス、透明セラミックス、セラミックス系複合材料など、先端無機材料を中心とした研究開発を行っている。
規模、研究開発力、研究成果などで、中国科学院内でトップレベルとなっている。

1. 名称
○中国語表記:上海硅酸盐研究所 略称 上海硅酸盐所
○日本語表記:上海珪酸塩研究所
○英語表記:Shanghai Institute of Ceramics 略称 SICCAS
2. 所在地
上海珪酸塩研究所本部の所在地は、上海市長寧区定西路1295号である。長寧区は上海市の中心にあり、上海虹橋国際空港から近く、区内西部の虹橋経済開発区は国際貿易センター、世界貿易センター、万都センターなどが林立するビジネス街である。また、日本人が多く居住する地区でもあり、在上海日本総領事館も長寧区にある。
首都・北京市ほどではないが、上海市には中国科学院の附属研究所が多く存在する。本HPでは、これまで上海マイクロシステム・情報技術研究所と上海光学精密機械研究所を取り上げてきており、今回は上海珪酸塩研究所を取り上げる。上海にある中国科学院附属の研究所全体像については、下記8.の特記事項を参照されたい。
3. 沿革
(1)源は中央研究院の工学研究所
1911年に辛亥革命が成功し中華民国が成立した後、袁世凱や軍閥の台頭などの混乱期を経て、1925年に国民党による国民政府が成立した。国民政府は1927年11月、近代的な科学技術や学術研究の重要さを認識し、中華民国の最高研究機関として「中央研究院」を政府直属で設立した。
翌1928年4月、蔡元培を初代の院長に選出した。蔡元培は中華民国の時代に、北京大学学長、中央研究院院長、国立中央博物館の館長などを務めた人物であり、詳しくはこちらを参照されたい。
中央研究院は同年、傘下の研究所を南京、上海、広州にいくつか設置したが、その一つが、上海に設置された工学研究所(工程研究所)であり、これが現在の上海珪酸塩研究所の源である。初代所長には、庚款留学生として米国で学んだ周仁・南洋大学(現上海交通大学)機械工学科長が任命された。
(2)日中戦争の戦火を避けて雲南省昆明に疎開
1937年の盧溝橋事件により勃発した日中戦争中、中央研究院傘下の研究機関は戦乱を避けて昆明、桂林、重慶等へ疎開したが、工学研究所も1938年に雲南省昆明に移転した。
1945年に日本が第二次世界大戦に敗北し、日本軍が大陸から撤退すると、工学研究所は翌1946年6月に上海に戻った。
(3)中国科学院の冶金セラミックス研究所
国共内戦が中国共産党の勝利に終わり、1949年に中華人民共和国が建国され、科学技術の最高機関として中国科学院が設置された。
中国科学院は発足後、これまでの中国の科学技術・学術研究の遺産ともいえる中央研究院の施設や人員の接収を行ったが、その一環で上海に戻っていた工学研究所も1950年3月に接収し、名称が中国科学院・工学実験館(工学实验馆)とした。
1953年には、名称を「冶金セラミックス研究所(冶金陶瓷研究所)」と変更した。
(4)独立して珪酸塩化学・工学研究所
1959年に、この冶金セラミックス研究所が2つに分かれ、セラミックス研究部門が「珪酸塩化学・工学研究所(硅酸盐化学与工学研究所)」となった。これが現在の上海珪酸塩研究所の前身である。
一方、冶金セラミックス研究所の残りの部分は「冶金研究所」となったが、これが現在の「上海マイクロシステム情報研究所(上海微系统与信息技术研究所)」である。
(5)文化大革命中の混乱
文化大革命が始まると、珪酸塩化学・工学研究所は中国科学院から切り離され、1968年に国防科学技術委員会傘下の第十六研究所(別名・無機非金属材料研究所(无机非金属材料研究所)となり、さらに人民解放軍の研究所となった。
(6)中国科学院に復帰
文化大革命の初期の混乱が収まった段階で、元々中国科学院にあった附属研究所の復帰が始まり、軍にあったこの研究所も1970年に中国科学院に復帰し、研究所名が「上海珪酸塩化学・工学研究所(上海硅酸盐化学与工学研究所)」となった。
1984年に、「上海珪酸塩研究所(上海硅酸盐研究所)」となり、現在に至っている。
4. 組織の概要
(1)研究分野
上海珪酸塩研究所は、先端無機材料を中心として研究開発を行っており、具体的な分野は高性能構造セラミックス、機能性セラミックス、透明セラミックス、セラミックス系複合材料、人工結晶、無機コーティング、エネルギー材料、生体材料、古代セラミックス、先端無機材料,関連性能・特性試験などである。
(2)研究組織
①国家級の研究室・実験室
・高性能セラミックス・超微細構造国家重点実験室(高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室)後述する
②中国科学院級研究室・実験室
・中国科学院無機機能材料・デバイス重点実験室(中国科学院无机功能材料与器件重点实验室)
・中国科学院透明光機能無機材料重点実験室(中国科学院透明光功能无机材料重点实验室)
・中国科学院エネルギー変換材料重点実験室(中国科学院能量转换材料重点实验室)
・特殊無機コーティング重点実験室(中国科学院特种无机涂层重点实验室)
・中国科学院先進構造セラミックス・複合材料重点研究室(中国科学院先进结构陶瓷及复合材料重点实验室)
③研究所級研究センター(例示)
・情報機能材料研究センター(信息功能材料研究中心)
・特殊無機コーティング研究センター(特种无机涂层研究中心)
・人工結晶研究センター(人工晶体研究中心)
・透明セラミックス研究センター(透明陶瓷研究中心)
・エネルギー材料研究センター(能源材料研究中心)
・生体材料・組織工学研究センター(生物材料与组织工程研究中心)
・古代陶磁器・工業陶磁器工学研究センター(古陶瓷与工业陶瓷工程研究中心)
・新素材パイロットプラント研究開発センター(新材料中试研发中心)
・無機材料分析試験センター(无机材料分析测试中心)
(3)研究所の幹部
上海珪酸塩研究所の幹部は、中国共産党委員会(党委)書記、所長、副所長、党規律委書記である。中国科学院の付属研究所の場合には所長が最高責任者の場合が多いが、現在の上海珪酸塩研究所では、中国国内の大学と同様、党委書記の方が序列上位となっている。
①王東・党委書記
王東(王东)上海珪酸塩研究所党委書記は、副所長も兼務しており、1970年に生まれ、1988年に浙江大学材料科学・工学科に入学して学士の学位を取得し、1999年にやはり浙江大学から博士学位を取得した。その後、上海珪酸塩研究所に入所し、2013年に同研究所副所長兼共産党規律委員会書記となり、2022年に党委書記となった。専門分野は、新しい強誘電体・圧電材料の作製とデバイス設計、高効率発光材料の作製と発光メカニズムの研究である。
②蘇良碧・所長
蘇良碧(苏良碧)上海珪酸塩研究所所長は、1979年に湖北省で生まれ、2000年に武漢理工大学で学士の学位を、2002年にやはり武漢理工大学で修士の学位を、2005年に中国科学院上海光学精密機械研究所で博士の学位をそれぞれ取得した。その後上海光学精密機械研究所を経て、2008年に上海珪酸塩研究所の研究員となり、2019年に副所長となった。2023年から所長を務めている。専門はレーザーや光学結晶材料の研究である。
5. 研究所の規模
(1)職員数
上海珪酸塩研究所の2021年現在の職員総数は759名で、中国科学院の中では第28位に位置する(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。759名の内訳は、研究職員が651名(86%)、技術職員(中国語で工員)が50名(6%)、事務職員が58名(8%)である。
(2)予算
2021年予算額は11億8,370万元で、中国科学院の中では第19位に位置する(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。11億8,370万元の内訳は、政府の交付金が3億5,262万元(30%)、NSFCや研究プロジェクト資金が2億4,900万元(21%)、技術収入が3億0,774万元(26%)、試作品製作収入が1億7,838万元(15%)、その他が9,596万元(8%)となっている。
(3)研究生
上海珪酸塩研究所の2021年現在の在所研究生総数は510名で、中国科学院の中で30位までのランキングには入っていない(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。510名の内訳は、修士課程の学生が243名、博士課程の学生が267名である。
6. 研究開発力
(1)国家級実験室など
中国政府は、国内にある大学や研究所を世界レベルの研究室とする施策を講じている。この施策の中で最も重要と考えられる国家研究センターと国家重点実験室であり、中国科学院の多くの研究機関に設置されている(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。上記組織の項でも述べたが、上海珪酸塩研究所は1つの国家重点実験室を有している。
・高性能セラミックス・超微細構造国家重点実験室(高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室):1989年に中国科学院の重点実験室としてスタートし、1991年に国の認可を受けて国家重点実験室となった。新先端無機材料の多層構造設計・性能・構造研究、無機材料製造研究、無機ナノ材料・メソポーラス材料研究、新無機材料探索・計算材料科学の研究を行っている。2021年現在で、正規研究員が名、客員研究員が116名、研究生としてポスドク84名、博士学生162名、修士学生76名である。
(2)大型研究開発施設
中国科学院は、同院や他の研究機関の研究者の利用に供するため大型の研究開発施設を有している。大型共用施設は、専用研究施設、共用実験施設、公益科学技術施設の3つのカテゴリーがある(中国科学院内の設置状況詳細はこちら参照)。上海珪酸塩研究所は、このような大型共用施設・共用実験施設は有していない。
(3)NSFC面上項目獲得額
国家自然科学基金委員会(NSFC)の一般プログラム(面上項目、general program)は、日本の科研費に近く主として基礎研究分野に配分されており、中国の研究者にとって大変有用である。上海珪酸塩研究所のNSFCの獲得資金額は、中国科学院の中で20位までのランキングには入っていない(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。
7. 研究成果
(1)Nature Index
科学雑誌のNatureは、自然科学系のトップランクの学術誌に掲載された論文を研究機関別にカウントしたNature Indexを公表している。Nature Index2022によれば、上海珪酸塩研究所は中国科学院内第12位であり、論文数は32.39となっている(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。
このNature Index に関し、中国の主要大学のそれと比べると高くない。中国の主要大学のNature Indexによるランキングは、こちらを参照されたい。
(2)SCI論文
上記のNature Indexはトップレベルの論文での比較であり、より多くの論文での比較も重要である。しかし、中国科学院は各研究所ごとの論文数比較を出来るだけ避け、中国科学院全体での比較を推奨している。このため、SCI論文などで研究所ごとの比較一覧はない。
(3)特許出願数
2021年の上海珪酸塩研究所の特許出願数は315件で、中国科学院内で第19位である(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。
(4)成果の移転収入
2021年の上海珪酸塩研究所の研究成果の移転収入は、中国科学院内でランキング外である(他の研究所との比較の詳細はこちら参照)。
(5)両院院士数
中国の研究者にとって、中国科学院の院士あるいは中国工程院の院士となることは生涯をかけての夢となっている。2025年2月時点で上海珪酸塩研究所に所属する両院の院士は5名であり、中国科学院内でランキング外である(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。
○中国科学院院士(2名):施剑林、陈立东
○中国工程院院士(3名):丁传贤、江东亮、董绍明
8. 特記事項~中国科学院における材料科学関連研究機関
現代の科学技術においてナノテクノロジーなどの材料科学は重要な分野であり、中国科学院内にも以下のように多くの材料研究機関がある。研究機関名をクリックすると、その機関の記事が開かれる。
・金属研究所
・理化技術研究所(理化技术研究所)
・プロセス工学研究所 (过程工程研究所)
・上海珪酸塩研究所(上海硅酸盐研究所) この記事
・国家ナノ科学技術センター(国家纳米科学中心)
・福建物質構造研究所(福建物质结构研究所)
・寧波材料技術・工学研究所(宁波材料技术与工程研究所)
・蘇州ナノテク・ナノバイオ研究所(苏州纳米技术与纳米仿生研究所)
・合肥物質科学研究院(合肥物质科学研究院)
・深圳先進技術研究院
参考資料
・中国科学院統計年鑑2022 中国科学院発展企画局編
・中国科学院年鑑2022 中国科学院科学伝播局編
・上海珪酸塩研究所HP https://www.sic.ac.cn/