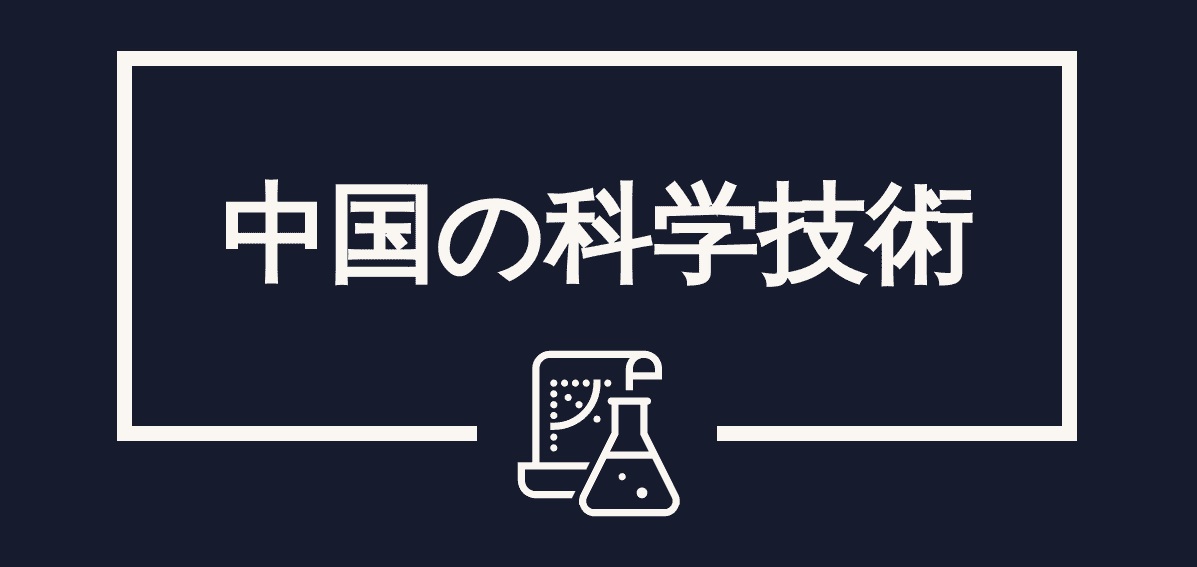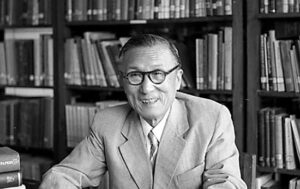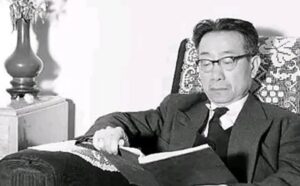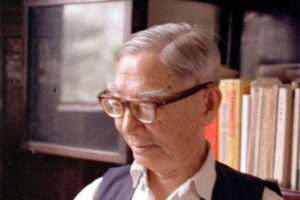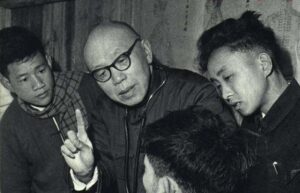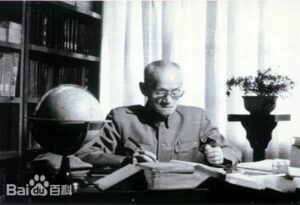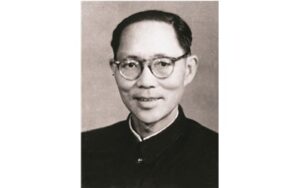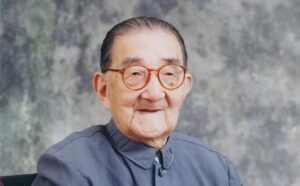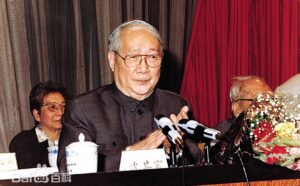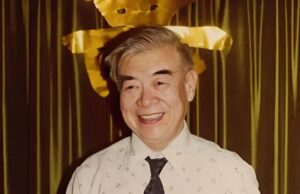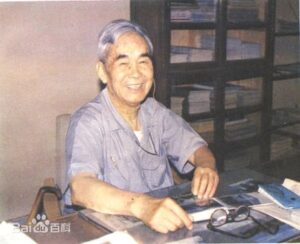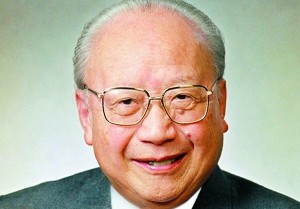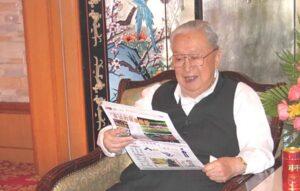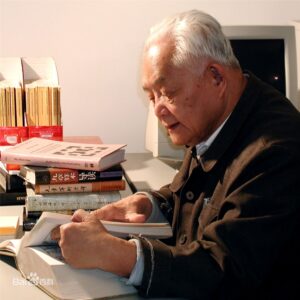中華人民共和国建国後に、科学技術における物理、数学、化学、工学、農学など各分野において、傑出した研究成果を挙げ中国における開拓者的な役割を果たした科学者・技術者を取り上げる。
秉志(Zhi Bing、1886年~1965年)
秉志は、清朝末期に生まれ、庚款留学生制度で米国のコーネル大学に留学し、帰国後は南京大学などで教鞭を取り、中国の近代動物学の基礎を築いた。
丁穎(Ying Ding、1888年~1964年)
丁穎は、日本に留学し第五高等学校や東京帝国大学で学んだ後、帰国してイネの品種改良を進め、新中国建国後は中国農業科学院の初代院長として近代農学の基礎を築いた。
李四光(Siguang Li、1889年~1971年)
李四光は、中国における地質学研究の基礎を築き、新中国となってからも国家の発展に必要な国内資源開発に貢献した。李四光は日本にも留学している。
侯德榜(Debang Hou、1890年~1974年)
侯德榜は、米国のMITやコロンビア大学に学んで、化学工学を学び、帰国して近代中国の化学工業の基礎を築いた。
竺可楨(Coching Chu、1890年~1974年)
竺可楨(竺可桢)は、卓越した気象学者として中国の学術の発展に寄与し、新中国建国後は中国科学院の発展を牽引した。
周仁(Ren Zhou、1892年~1973年)
周仁は、冶金学者、セラミック学者であり、国民政府時代の中央研究院工程研究所の所長や、その後継機関である中国科学院冶金セラミックス研究所や冶金研究所などの所長を45年にわたって務めた。
陳建功(Jiangong Chen、1893年~1971年)
陳建功(陈建功)は、三度にわたり日本に留学し、東北帝国大学で外国人初めてとなる博士学位を取得し。その後中国に帰国して、後輩の蘇歩青と共に「陳蘇学派」を形成して母国の数学研究・教育に貢献した。
熊慶来(Qinglai Xiong、1893年~1969年)
熊慶来(熊庆来)は、フランスで数学を学んだ後帰国し、清華大学などで多くの数学者を育てた。華羅庚はその代表的な数学者である。
金善宝(Shanbao Jin、1895年~1997年)
金善宝は、米国のコーネル大学やミネソタ大学で学んで帰国し、中国の小麦の品種改良に貢献して「小麦大王」と呼ばれた農学者である。
茅以升(Yisheng Mao、1896年~1989年)
茅以升は、米国留学後に帰国して橋梁工学の基礎を築き、中国の現代橋梁の父と呼ばれた技術者である。茅以升は、中国国内の著名な橋梁建設の指揮を執るとともに、人民大会堂の建設設計にも携わっている。
呉有訓 (Youxun Wu、1897年~1977年)
呉有訓 (Youxun Wu、1897年~1977年)は米国のシカゴ大学に留学し、アーサー・コンプトン教授の下で「コンプトン効果」の実証に取り組み、コンプトンのノーベル賞受賞に貢献した後、中国に帰国し、清華大学理学院長として数々の優れた物理学者を育てている。
湯飛凡 (Feifan Tang、1897年~1958年)
湯飛凡 (汤飞凡)は、国民政府時代から新中国初期に活躍した細菌学者であり、眼の病であるトラコーマ治療でも画期的な成果を挙げたが、文革前の反右派闘争で批判され、自ら命を絶っている。
張孝騫(Xiaoqian Zhang、1897年~1987年)
張孝騫は、米国に留学して医学を学び、帰国後に近代内科学の基礎を築いた。また、医学教育にも力を注ぎ、北京協和医学院や湘雅医学院の発展に寄与した。
厳済慈(Jici Yan、1901年~1996年)
厳済慈は、物理学者として業績を挙げるとともに、中国科学院傘下の中国科学技術大学と中国科学院大学の発展に大きく貢献した。
林巧稚(Lin Qiaozhi、1901年~1983年)
林巧稚は、著名な女医であり、中国女性初という栄誉をいくつか獲得している。林巧稚は努力を重ねて近代の科学技術の歴史に名を残した。
張鈺哲(Yuzhe Zhang、1902年~1986年)
張鈺哲は、近代天文学を欧米から導入し、中国の近代天文学の基礎を築いた。中国は古代文明の発祥地の一つであり、人民統治の重要な手段を提供する天文学が発展してきた。しかし、物理学の理論や望遠鏡などを用いた近代的な天文学は、他の科学技術と同様に遅れてスタートしている。
蘇歩青(Buqing Su、1902年~2003年)
蘇歩青は、微分幾何学などで業績を残し上海の名門復旦大学などで多くの優秀な弟子を育てたことにより、中国の「数学王」と呼ばれている。日本に留学し日本人女性と結婚しその子息の一人が現在も日本で活躍している。
童第周(Dizhou Tong、1902年~1979年)
童第周は、世界初の魚類クローンを作製して中国のクローン技術の基礎を築き、クローン技術の先駆けを成し遂げた。童第周の貢献もあり、中国では現在でもクローン技術で世界トップレベルを誇っている。
周培源(Peiyuan Zhou、1902年~1993年)
周培源は、一般相対性理論や乱流の研究で有名な物理学者であり、文革終了後に北京大学学長を務めている。
趙忠堯(Chung-Yao Chao、1902年~1998年)
趙忠堯(赵忠尧)は、カリフォルニア工科大学に留学しノーベル賞クラスの実験を行った後、中国の原子科学の研究と教育の発展に尽力した。
呉学周(Xuezhou Wu、1902年~1983年)
呉学周(吴学周)は、分光法や反応速度理論で成果を挙げた物理化学者で、30年近くにわたり長春物理化学研究所所長を務めた。
貝時璋(Shizhang Bei、1903年~2009年)
貝時璋は、中国において発生生物学や細胞生物学などの近代的な生物学研究を推進した科学者である。107歳という長寿を全うし、創設時からの中国科学院院士であったことから、親しみを込めて「長寿院士」と呼ばれた。
裴文中(Wenzhong Pei、1904年~1981年)
裴文中は、北京郊外の周口店で、考古学の歴史的発見と言われる北京原人の完全に近い頭蓋骨を発見し、中国の考古学発展の基礎を築いた。
沈其震(Qizhen Shen、1907年~1993年)
沈其震は、中国で医学の基礎を学んだ後、日本の東京大学に留学した。帰国後、共産党軍に身を投じ、日中戦争などで軍の医学的な顧問を務め、新中国建国後は初代の中国医学科学院院長に就任した。
呉大猷(Ta-You Wu、1907年~2000年)
呉大猷(吴大猷)は、米国ミシガン大学に留学し、北京大学などで教鞭を執り、ノーベル賞学者の楊振寧や李政道を育てた。晩年は台湾に移り、台湾の中央研究院の院長などを務めた。
華羅庚(Luogeng Hua、1910年~1985年)
華羅庚は、貧しい家庭環境から高等教育を十分に受けられなかったが、周囲の好意と幸運に恵まれて著名な数学者となり、中国数学界に偉大な功績を残した。彼は、日本に招聘され東大で学術講演中に心臓発作を起こし、東京で死去している。
張文裕(Wenyu Zhang、1910年~1992年)
張文裕(张文裕)は、高エネルギー物理研究所設立の端緒となった加速器建設を周恩来総理に提案し、その建設運営のため同研究所が設立されると初代の所長を務めた。中国の高エネルギー物理学を先導した科学者である。
銭偉長(Weichang Qian、1912年~2010年)
銭偉長は、弾性力学、爆発力学などで理論面での貢献をし、科学技術の発展に多大な足跡を残した。銭学森、銭三強と並んで中国科学界の「三銭」と呼ばれている。
李薫(Hsun Lee、1913年~1983年)
李薫(李薰)は、英国シェフィールド大学に留学した後、中国科学院金属研究所の初代所長となり、中国の冶金技術の確立に貢献した。
何沢慧(He Zehui、1914年~2011年)
何沢慧(何泽慧)は、ドイツやパリで研究を行った後、夫・銭三強と共に帰国し、高エネルギー物理研究所などので宇宙線研究を行った女性科学者である。
葉篤正(Duzheng Ye、1916年~2013年)
葉篤正(叶笃正)は、シカゴ大学に留学後に中国科学院で東アジアの大気循環などを研究して中国気象学の基礎を築き、国家最高科学技術賞などを受賞した。
呉階平(Jieping Wu、1917年~2011年)
呉階平(吴阶平)は、北京協和医学院を卒業した泌尿器科の著名な医師であり、周恩来やインドネシアのスカルノ大統領の主治医であったことでも有名である。
劉東生(Dongsheng Liu、1917年~2008年)
劉東生(刘东生)は、黄土高原やチベット高原の地質調査などを行った地質研究者で、国家最高科学技術賞などを受賞している。
師昌緒(Changxu Shi、1918年~2014年)
師昌緒(师昌绪)は、米国に留学した冶金学者で、中国科学院金属研究所で航空機用の耐熱合金、新型高性能合金等の開発を行い、国家最高科学技術賞を受賞した。
呉文俊(Wenjun Wu、1919年~2017年)
呉文俊(Wu Wenjun、吴文俊、1919年~2017年)は、台数トポロジーの研究で成果を挙げた数学者であり、ウー類(Wu classes)やウーの公式にその名を残している。
黄昆(Kun Huang、1919年~2005年)
黄昆は、固体物理学を基に半導体の理論的な研究の基礎を築いた。半導体は、産業のコメとも言われてIT産業などに不可欠な素材であり、中国でもその研究開発と産業化が熱心に進められている。
謝家麟(Jialin Xie、1920年~2016年)
謝家麟(谢家麟)は、BEPCの建設など中国の加速器科学の確立に貢献し、2011年に国家最高科学技術賞を受賞した。
謝希徳(Xie Xide、1921年~2000年)
謝希徳(谢希德、1921年~2000年)は、固体物理学や半導体科学を専門とした女性科学者であり、1983年には女性として中国史上で初めて主要大学の一つである復旦大学学長を務めた
呉孟超(Mengchao Wu、1922年~2021年)
呉孟超(吴孟超、Wu Mengchao、1922年~2021年)は、中国の外科医・医学者であり、肝臓・胆管の外科手法などを開発し、「中国肝胆外科の父」と呼ばれている。
王振義(Zhen-yi Wang、1924年~)
王振義(王振义)は、血液学の研究で成果を挙げた医学者で、上海第二医科大学の学長も務め陳竺元衛生部長など多くの人材を育て、国家最高科学技術賞や未来科学大賞などを受賞している。
張存浩(Cunhao Zhang、1928年~2024年)
張存浩(张存浩)元中国科学院大連化学物理研究所長は、中国の化学レーザー研究の基礎を築き、2013年には国家最高科学技術賞を受賞している。
金怡濂(Yilian Jin、1929年~)
世界では、日本、米国と並んで中国がスパコン開発の中心国である。金怡濂は、中国の工学者でスパコン「神威・太湖之光」の開発の指揮を執り、同機は計算速度で世界一の座を2年間維持した。
袁隆平(Longping Yuan、1930年~2021年)
中国では、食糧確保のための農業振興は重要事項である。袁隆平は、世界的な業績と言われハイブリッド米を開発した農学者である。
李方華(Li Fanghua、1932年~2020年)
李方華(李方华、1932年~2020年)は、ソ連のレニングラード大学に留学し、中国科学院物理研究所で電子顕微鏡の研究を行った女性物理学者であり、大阪大学にも留学して橋本初次郎教授に師事している。
陳景潤(Jing-Run Chen、1933年~1996年)
陳景潤(陈景润)は、恩師華羅庚の助力を得、逆境を何度か乗り越えて、ゴールドバッハ予想の一つを解決した数学者である。
ウシ・インスリン合成~鈕経義と鄒承魯
ウシ・インスリン合成プロジェクトは、集団での研究開発成で有名である。プロジェクトの概要と研究者の鈕経義(钮经义)と鄒承魯(邹承鲁)を取り上げる。