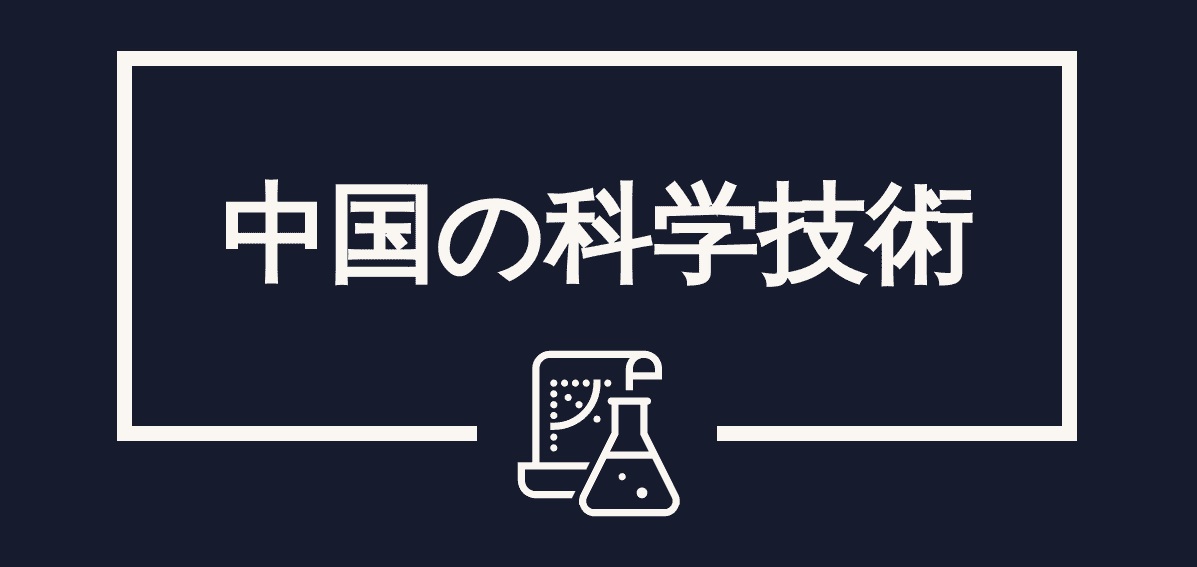はじめに
楊煥明(杨焕明、Yang Huanming、1952年~)は、ゲノム解読企業であるBGIの共同創設者であり、世界のゲノム解読関連分野をけん引している科学者である。

生い立ちと教育
楊煥明(杨焕明、Yang Huanming)は、1952年に浙江省温州市に生まれた。温州市は東シナ海に面する海上交通の要路であり、南宋以降には対外通商の拠点として発展した。温州人は商才があり、温州商人としてヨーロッパを中心に世界で活躍している。
楊煥明は5人兄弟で、家はそれほど豊かではなかった。生まれた場所は、山と海が近接し半農半漁で生計を立てる小さな村であった。農業での収穫は干ばつにより脅かされることが多く、母は毎日曜日に海に行って魚やカニを取ってくるよう楊煥明に命じた。
そんな生活ではあったが、楊煥明は幼いころから大の読書好きで、暗い夜でもランプの灯に頼って読書に励んだ。
小学校を卒業し、地元の中学校の時の1966年に文化大革命が勃発して、学業を中断せざるを得なくなった。文革は、極端な反エリート主義・反知性主義の側面を有していて、中央の官吏、大学の教授などはもちろん、地方の小学校や中学校の先生まで批判や迫害の対象となった。
文革の暴力的な側面を抑えるため、毛沢東は「若者たちは貧しい農民から再教育を受ける必要がある」として、若者たちを都市から内陸部の農村に送り労働に従事させた。これを下放(上山下郷運動)と呼んでいる。
楊煥明も、中途半端な授業ではあったが中学校を卒業し、その後この下放の対象となり、近くのビール醸造工場での労働に従事した。楊煥明はまじめに労働に従事したため、上司の主任技術者に可愛がられ、醸造に係る微生物学などを教えてもらった。
杭州大学に入学
当時、大学入学試験(高考)が停止となっており、技術者などの育成を心配した政府は、下放などで労働に従事した若者を対象として、共産党や文革の革命委員会などの推薦により大学に入学させる制度を1971年から開始した。
楊煥明は、この制度により上司の推薦を受け、23歳となった1975年に杭州大学(現在の浙江大学の一部)生命科学院に入学した。
楊煥明は3年後の1978年に杭州大学を卒業し、学士学位を取得して故郷の温州医学院(現在の温州医科大学)に勤務したが、翌1979年には南京鉄道医学院(現在は東南大学の一部)生物系の大学院生となった。
楊煥明は、1982年に南京鉄道医学院から修士学位を取得し、その後同校の生物学講師となった。
デンマークに留学
1984年、楊煥明はデンマークのコペンハーゲン大学の医学遺伝学研究所に留学した。1988年に同大学から博士学位を取得した。
楊煥明は博士学位取得後、欧州の研究機関や米国の大学(ハーバード大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校)でポスドク研究を行った。
楊煥明は1994年に帰国し、北京にある中国協和医科大学(現在の北京協和医学院)の教授となった。
さらに1998年には、やはり北京にある中国科学院遺伝研究所(現在の遺伝・発生生物学研究所)に転籍して、同研究所のヒトゲノム研究センターの主任となった。
BGIを設立
楊煥明は中国科学院に在籍中の1999年に、友人である汪建(Wang Jian、1954年~)らとともに、民間の研究機関として北京華大基因(北京华大基因、Beijing Genomics Institute:BGI)を立ち上げた。
BGIが設立された当時、世界の生命科学は大きな変革のさなかにあった。1990年から、生命科学分野では初めてといってよい大型国際協力プロジェクトである「ヒトゲノム計画」が、米国の主導により日本や欧州の国々の参加を得て開始されていた。
楊煥明は、シーケンス技術の意義や重要性を敏感に感じ取り、BGIを立ち上げることで当時終盤にさしかかっていたヒトゲノム計画への途中参加を中国政府に働きかけて資金拠出を約束させた。そして、同計画で中国へ割り当てられた1%分のゲノム解読を全て行ったことにより、楊煥明は中国におけるゲノム研究の第一人者となり、またBGIは中国国内のみならず国際的な信用を得ることとなった。

浙江大学生命科学学院HPより引用
このヒトゲノム計画とは別に「HapMap計画」が2002年10月にスタートしたが、中国はこの計画に米国、英国、カナダ、ナイジェリア、日本と共に当初から参画し、楊煥明は中国側の責任者となり、中国の担当分である全体の10%のうち相当部分の解析を行った。
また、BGIは、2003年2月に発生したSARSのゲノム解読を行うとともにタンパク質解析を行ってウイルス検査キットの開発を行った。2004年にスマトラ島沖地震が発生し大津波により20万人以上が死亡した際も、BGIはチームをタイに派遣し、DNA解析を用いることにより身元確認に多大な貢献を行った。
このような貢献が中国国内で評価され、2003年末には民間の機関から政府直轄機関として中国科学院の研究機関に格上げされた。
しかし、業務の進め方を巡って中国科学院の伝統的な考え方と楊煥明らBGIの大量のシーケンスを組織的に行うという進め方で意見対立が発生した。その結果中国政府から冷遇され、2006年3月に策定された「国家科学技術第11次五か年計画(2006年〜2010年)」では、BGIが要望したプログラムが全く採用されず、結果として中国政府からの拠出はほとんど無くなってしまった。
深圳市の助力を得て、深圳市に移転して再建
そのような楊煥明らBGIの窮地を救ったのが、中国南部の広東省にある深圳市だった。同市は、BGIに対し4年間で2千万元(約3.2億円)の資金を拠出した。
BGIは、2007年4月に深圳政府から靴工場の跡地提供を受けて、北京から深圳に移転した。それ以降、BGIは北京華大基因というかつての正式名で呼ばれることはなくなり、略称であったBGI自体が正式名称になった。中国語では、「華大基因」と呼ばれている。
世界のゲノム解読工場へ
2010年、中国の国家開発銀行はBGIに対し百億元の信用供与枠を供与した。BGIはその資金を用いて、販売が開始されたばかりの最新の機能を有する米国イルミナ社のシーケンサー「HiSeq2000」を128台も大量購入し、BGI一社だけで米国全体のシーケンス能力を凌駕する規模となった。これはBGIの存在を全世界に知らしめた出来事であり、大量のシーケンサーを用いてシーケンスを行うことにより、世界のシーケンス工場としての地位を確立した。
このシーケンサーの大量購入には、楊煥明の考えが大きく働いている。
楊煥明は、シーケンサーの重要性を早くから見抜き、シーケンスとバイオインフォマティクスに焦点を絞って活動を行った。ゲノム研究そのものにはそれほど重きを置かず、シーケンス作業をサービスとして請け負うという考えを徹底させた。関係者の中にはBGIは工場であって研究所ではなく創造性がないという非難がなされた。しかしイルミナ社に大量発注した時点を考えると新たな機器開発では米国がはるか先を進んでおり、楊煥明らは開発された機器を見極めて多く購入しそれを用いて多くのゲノム解読を行うことに意義があると考えたのである。
現在においてもBGIの特徴は、多くの人員を雇用して大量かつ組織的に解読を行うということにある。また、BGIのスタッフの年齢は非常に若い。BGIはグループ内部に、バイオ分野の人材を育てる教育機関「華大基因学院」を設置し、学位を持たない者でも短期間にゲノム解析やバイオインフォマティクスを習熟できるように体制を整えている。
BGIの更なる発展を指揮
BGIはさらに現在発展し、かつては米国のイルミナ社からの大量購入したシーケンサーを、BGI自らが開発し、すでに中国国内を中心として販売している。
また、シーケンス事業とは少し離れるが、中国政府の委託を受けて国家遺伝子バンクを設置運営する事業に参画している。このバンクは、深圳市が10億ドルかけて整備したのち、運営をBGIに委託しているものであり、深圳の中心部から東50キロにある大鵬新区の5ヘクタールの土地に世界最大の施設として建設され、2016年9月から稼働している。

楊煥明はBGIの理事長(日本の企業の社長)として、盟友である汪建BGI董事長(日本の企業の会長)とともに、引き続き中国のゲノム関連の研究開発をけん引している。
楊煥明と日本との関係であるが、日本経済新聞社は2003年に楊煥明に「日経アジア賞」を授与している。この時の肩書は北京ゲノム研究所主任であり、授賞理由は「長粒種イネ(インディカ米)のゲノム解読を世界で初めて実現した グループの中心人物」であった。
参考資料
・华大(BGI)集团HP https://www.genomics.cn/
・浙江大学生命科学学院HP 薪火相传生科人|杨焕明:探微求真 丹心育才 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzE3MTQ4MA==&mid=2651852608&idx=1&sn=87a342e013ea58fa8f9f0254278fe9ce&chksm=85aca7884e9155e9787a111dcbcf88421e5ffcd872a9f502008f900f26b0527960198ce64171&scene=27
・日経アジアアワードHP https://nikkeiasiaaward.org/jp/pastwinners/index.html
・本HPのBGIの記事 https://china-science.com/bgi-lifescience-china/