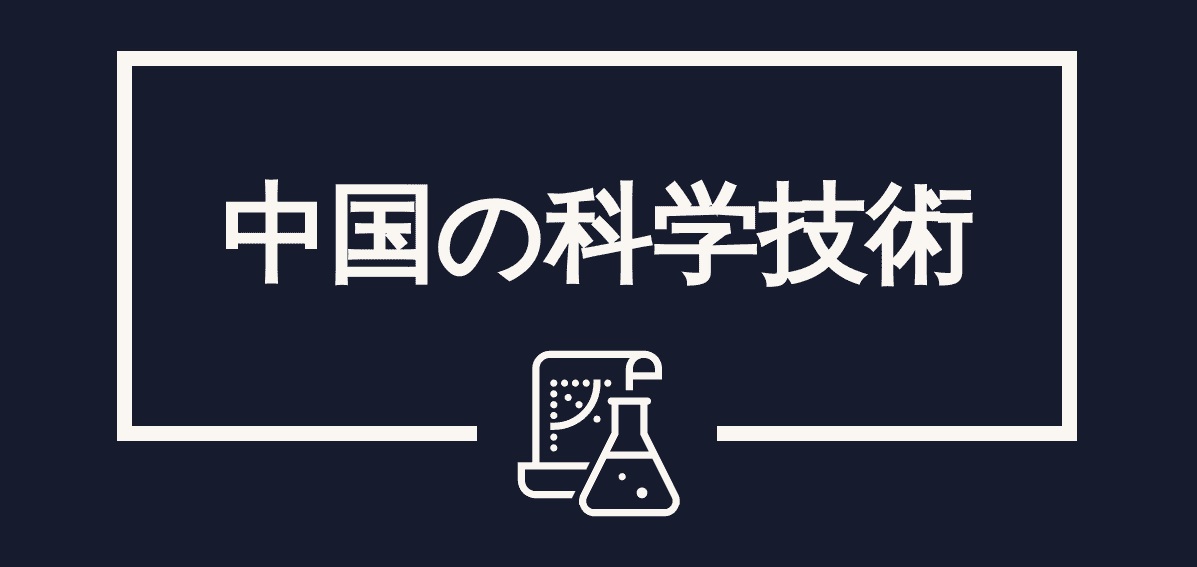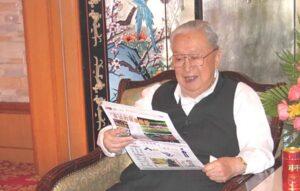はじめに
劉東生(刘东生)は、黄土高原やチベット高原の地質調査などを行った地質研究者で、国家最高科学技術賞などを受賞している。

生い立ちと教育
劉東生(刘东生、Dongsheng Liu)は、1917年に遼寧省瀋陽に生まれた。父は鉄道の副駅長を務めていた。
劉東生は、5歳から私塾で学び、1930年に天津にあった南開中学に入学した。南開中学は、1895年の日清戦争敗北を受けて日本の教育制度を参考に1904年に開校した中学校(日本の高校教育も含まれる)であり、新中国となってから国務院総理を務めた周恩来が、日本に留学する前の1917年に卒業している。
劉東生は、在学中に腸チフスに罹り休学したため、1937年に漸く南開中学を卒業した。
国立西南連合大学に入学
南開中学の卒業生は系列校の南開大学に無試験で入ることが出来たが、1937年7月に盧溝橋事件が起き、日中戦争が始まって天津が日本軍に占領されたため、南開大学は北京大学や清華大学と共に、西部への疎開を余儀なくされた。
劉東生は、天津の外国租界などに身を隠して様子を見ていたが、翌1938年に雲南省昆明に南開大学など3大学が国立西南連合大学を設置したと聞き、東南アジアを経由して昆明に到着して同大学に入学した。
父は大学での専攻を機械工学とするよう勧めていたが、劉東生はこれを無視して地質・地理・気象学科に入学した。1942年に国立西南連合大学を卒業したが、再び病気となり長期の療養生活を送った。病気から回復すると、劉東生は抗日戦線の野戦部隊などで補助的な業務に就いた。
中央地質調査所を経て中国科学院地質研究所へ
劉東生は1946年に、南京にあった中央地質調査所(北平研究院の地質調査所が前身)の技師として採用された。研究者としては、29歳という遅いスタートであった。
1949年に新中国が建国され、直後に中国科学院が設置された。中国科学院は、中央研究院や北平研究員の人材や設備等を接収し、新たに多くの附属機関を設置していった。その一つとして、地質研究所が1951年に南京に設置され、中央地質調査所は改編された。
劉東生も、地質研究所の職員となった。
黄土高原やチベット高原を研究対象に
劉東生は、 1950年代から黄土の起源の探究に力を注ぎ、黄土高原で多数の現地調査と実験分析を行い、黄河中流域の黄土分布図、中国黄土分布図、および多数のモノグラフを完成させ、重要な突破口となる「新風成理論」を提唱し、黄土高原上部の黄土層から黄土層全体に風成堆積作用を拡大し、それまで輸送過程のみを重視していた風成効果を、起源-輸送-堆積-堆積後の変化という完全な過程にまで拡大した。中国の黄土に基づいて、過去250万年の気候変動の歴史が解明され、黄土、深海堆積物、極地氷床コアが環境変動研究の3つの柱となった。
また、劉東生は青海チベット高原の隆起と東アジアモンスーンの変化に関する研究を行い、地殻変動・気候科学理論のモデルを確立した。
1970年代には黄土の科学研究を継続し、第四紀地質学の発展を牽引した。国際的に認められた洛川黄土標準面を確立し、中国の黄土に基づいて過去250万年の気候変動の歴史を再構築した。
文化大革命で迫害を受ける
中国科学院の地球化学研究所が、1966年に江西省貴陽に設置されると、劉東生は同研究所に移動となり、第四纪地球化学研究室の主任となった。
ところがその直後に文化大革命が勃発し、劉東生は批判と迫害を受け、科学研究を続けることが不可能となった。劉東生は下放に会い、風土病が蔓延する地方に移動した。劉東生は、この機に風土病の研究を行った。これが、下放された地方の革命派幹部の賞嘆を得て、迫害から脱するきっかけとなった。
文革が終了した1977年に、劉東生は地球化学研究所の副所長に就任したが、2年後の1979年には貴陽の地球化学研究所から北京の地質研究所に戻っている。
国際研究交流に尽力
劉東生は、適齢期に日中戦争の戦乱があったり、病気となったりしたため、外国留学は経験しなかった。しかし、黄土高原やチベット高原といった世界でも注目される地質研究を行ってきたため、国際研究交流には積極的に参加している。以下にいくつかの例を挙げる
・1957年、劉東生は招待を受けてソ連に赴き、全ソ第四紀科学会議に出席し、中国の第四紀研究の現状を紹介した。
・1961年、劉東生は代表団の一員としてポーランドに赴き、中国の黄土と題した報告を行った。
・1976年、劉東生は食道がん原因総合調査チームのリーダーとして、ケニアナイロビで開催された国連環境計画の年次総会に出席した。
・1988年、劉東生は第5回永久凍土に関する国際会議に出席するためにノルウェーのトロンハイムを訪れた。同年9月、INQUA黄土委員会と古地理委員会の合同会議および南アルプス黄土に関する国際シンポジウムに出席するためイタリアのヴェローナへ赴いた。
・1996年、劉東生は北極圏の北緯78度13分に位置するスヴァールバル諸島へ赴き、調査を行った。
国家最高科学技術賞などを受賞
以上の様に国内外での活躍を受けて、劉東生は著名な賞を受賞している。
劉東生は、2002年にタイラー賞を受賞した。同賞は、環境科学、環境衛生学、エネルギーに関する賞であり、1973年に創立され、南カリフォルニア大学が運営している。
劉東生は、2003年に国家最高科学技術賞を受賞した。国家最高科学技術賞は、2000年に設置された中国最高の科学技術賞であり、日本の文化勲章に近く、国家主席により授与される。劉東生は、当時の国家主席であった胡錦濤より受賞している。

劉東生は、2008年に北京で亡くなった。享年91歳であった。
参考資料
・中国科学院HP 劉東生先生紀年展室 http://www.chiqua.org.cn/ldsxsjnzs/
・中国科学院地質・地球物理研究所HP 劉東生
http://www.igg.cas.cn/rcjy/yszj/200907/t20090717_2094702.html
・中国科学院地球化学研究所HP 劉東生院士
https://www.gyig.ac.cn/yjsgk_/yszj_/zys/202201/t20220105_6333796.html