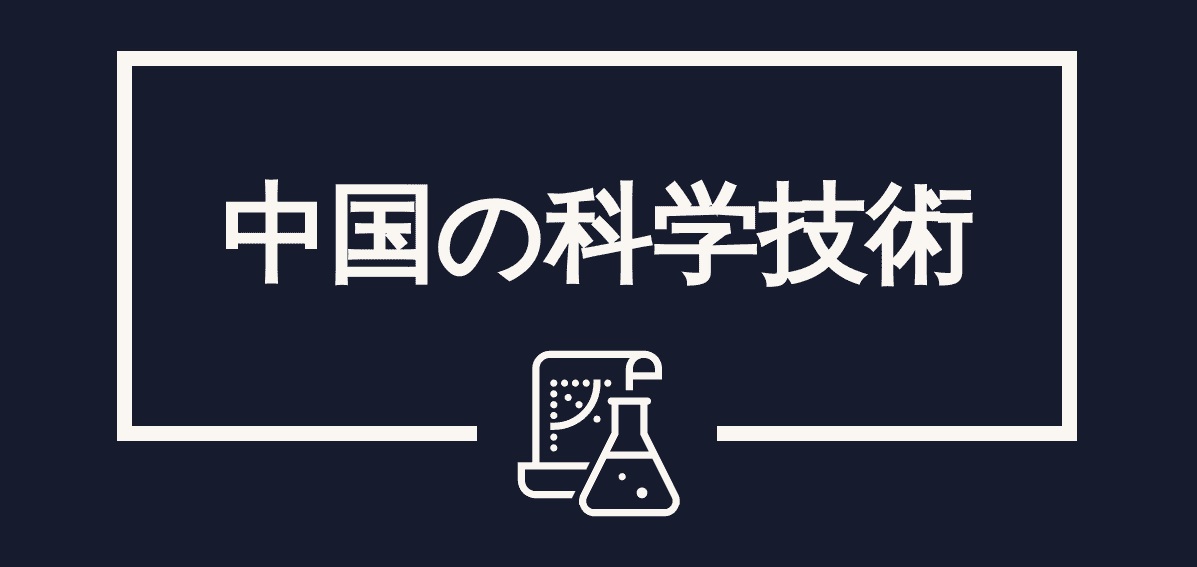はじめに
2025年10月6日から8日にかけて、ノーベル科学三賞の受賞者が発表された。今年は、日本人研究者が2名も受賞するという当たり年になった。この2名は林が予想した60名の候補者リストに入っている研究者であった。ただ、私がこの候補者リストを作成するきっかけとなった中国系の研究者の受賞は、残念ながら昨年に続きなかった。
以下にこれらについて、簡単な分析を行う。
1. ノーベル生理学・医学賞
・メアリー・E・ブランコウ(Mary E. Brunkow)システム生物学研究所シニア・プログラムマネージャー:著名国際賞や引用栄誉賞の受賞歴はない。(米国籍)
・フレッド・ラムズデル(Fred Ramsdell)ソノマ・バイオセラピューティクス社科学諮問委員会議長:クラフォード賞(2017年)。(米国籍)
・坂口志文(Shimon Sakaguchi)大阪大学特別教授:ガードナー国際賞(2015年)、トムソン・ロイター引用栄誉賞(2015年)、クラフォード賞(2017年)、ロベルト・コッホ賞(2020年)。(日本国籍)
なお、この生理学・医学賞の研究内容については、下記を参照されたい。
「2025年ノーベル賞特集 制御性T細胞を発見した坂口博士ら3人にノーベル生理学・医学賞」
2. ノーベル物理学賞
・ジョン・クラーク(John Clarke)カリフォルニア大学バークレー校名誉教授。(英国籍)
・ミシェル・デヴォレ(Michel Devoret)カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授。(フランス国籍)
・ジョン・M・マーティニス(John M. Martinis)カリフォルニア大学サンタバーバラ校名誉教授。(米国籍)
三名とも、著名国際賞や引用栄誉賞の受賞歴はない。
3. ノーベル化学賞
・北川進(Susumu Kitagawa)京都大学副学長:トムソン・ロイター引用栄誉賞(2010年)。(日本国籍)
・リチャード・ロブソン(Richard Robson)メルボルン大学教授:著名国際賞や引用栄誉賞の受賞歴はない。(英国籍)
・オマー・ヤギー(Omar M. Yaghi)カリフォルニア大学バークレー校教授:トムソン・ロイター引用栄誉賞(2010年)、キング・ファイサル賞(2015年)、ウルフ賞化学(2018年)、バルザン賞(2024年)。(ヨルダン、サウジアラビア、米国籍)
4. 注目点
(1)引用栄誉賞や著名国際賞の受賞状況
筆者のノーベル賞候補者の選定基準は、引用栄誉賞や著名な国際賞を受賞しているかどうかであった。
今年の場合、受賞者9名のうち引用栄誉賞は3名であり、また著名国際賞受賞者は3名であった。両方を受賞している人もいて、全体としては4名が受賞者であり、残りの5名は両方を受賞していなかった。ちなみに2024年の場合には、受賞者7名全員が、両方またはいずれかを受賞していた。
今後の改良点として、現在32としている著名国際賞の数を、もう少し増加させる方向で検討したいと考えている。
(2)ノーベル賞受賞者レベルでの米国の存在感
今回の受賞者を国籍別にみると、米国4名、日本2名、英国2名、フランス1名などとなっている。米国籍の科学者には、パレスチナ難民の子としてヨルダンで生まれ、15歳の時に米国に渡ったオマ・ヤギーカリフォルニア大学バークレー校教授を含んでいる。
また、ノーベル賞につながる研究を行った研究場所のある国で見ると、英国人とフランス人研究者は米国で研究を行っていて米国が6名、日本が2名、オーストラリアが1名となる。
さらに、坂口志文大阪大学栄誉教授は30代前半で渡米し、ジョンズ・ホプキンス大学、スタンフォード大学、スクリップス研究所、カリフォルニア大学サンディエゴ校などで約10年間研究を行っている。
このように、ノーベル賞の受賞者で見る限り、米国の存在感は圧倒的である。
ただし懸念もある。現在のトランプ政権の大学や研究機関への政策である。筆者から見ればトランプ大統領の政策は反知性主義の産物であり、かつて中国を大混乱に陥れた文化大革命や、ポルポト政権時代のカンボジアを彷彿とさせるものである。この政策が長く続くと、米国の科学技術の優位性が大きく揺らぐ可能性がある。このような反知性主義的な政策が、短期間に終了することを期待したい。
(3)中国との関係、残念だった日本人研究者
筆者がノーベル賞候補者を選定しようと思い立ったのは、中国の科学技術の状況分析の一環であり、その意味で中国系の科学者がノーベル賞受賞者に名を連ねてほしいという希望を持っている。しかし、今年も残念ながら中国系の科学者のノーベル賞受賞者はなかった。
ただ、今回のノーベル賞受賞者の中には、近年中国が設置した国際賞の受賞者が含まれている。今回物理学賞を受賞した3名のうち、ジョン・クラーク教授とミシェル・デヴォレ教授は、2021年に「Micius Quantum Prize(墨子量子賞:墨子量子奖)」という賞を受賞している。
この墨子量子賞は、中国の量子物理及び量子情報分野分野における国際的な影響力を拡大するため、中国安徽省の民間企業3社が共同で設置した墨子量子科技基金会が授賞するものであり、2018年から授与を開始している。受賞者には賞金100万元(約15万ドル)と金メダルが授与される。
中国には、量子通信などで世界的な成果を挙げた潘建偉(Jian-Wei Pan)中国科学技術大学副学長という優れた科学者もいて、量子物理分野は中国科学技術発展の重要な一分野となっている。
ちなみに、墨子(Mozi)は中国古代の戦国時代に活躍した諸子百家の一人であるが、これが量子科学の賞に冠されることになったのは、潘建偉副学長の主導により世界で初めて2016年に打ち上げられた量子通信科学実験衛星「墨子号(Micius)」に由来する。これらの業績により、潘建偉副学長は墨子量子賞の第二回(2019年)の受賞者となっている。

そして、ジョン・クラーク教授とミシェル・デヴォレ教授が2021年に墨子量子賞を受賞した際の共同受賞者に、日本の超伝導量子コンピュータや量子技術の権威である中村泰信東京大学大学院物理工学専攻教授がいた。今回のノーベル物理学賞の授賞理由が少し変われば、中村教授にも受賞の可能性があったと考えられ、極めて残念であった。

日本学士院ホームページより引用
参考資料
・日本学士院HP 第113回学士院賞 超伝導量子ビットとその量子制御に関する先駆的研究(共同研究)中村泰信
https://www.japan-acad.go.jp/pdf/youshi/113/nakamura_tsai.pdf