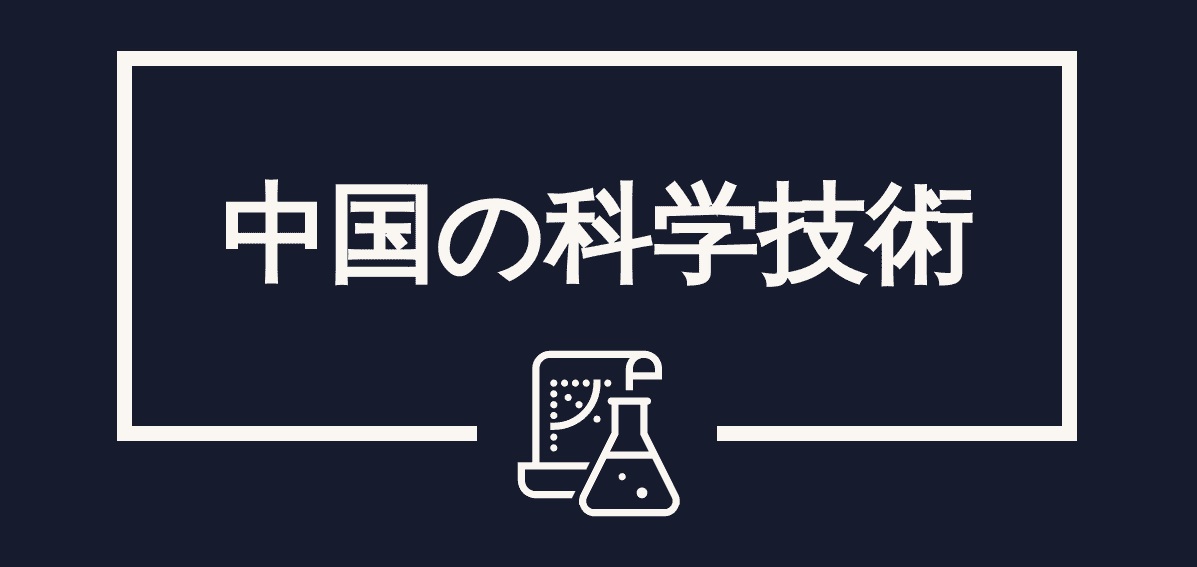Jiang-Zemin Era
1. 江沢民時代の歴史の流れ

(1)社会主義市場経済の導入と高度経済成長の開始
1992年8月、国務院は鄧小平の南巡講話を受け、科学技術を第一の生産力とし社会主義市場経済に適応したシステムを確立するため、「人材移転、構造調整、科学技術体制改革のさらなる深化に関する意見」を発表した。
1992年10月の中国共産党全国代表大会と翌1993年3月の全国人民代表大会で、鄧小平に代わって最高指導者としての地位を確実なものとした江沢民中国共産党総書記は、改革開放政策を継承と「社会主義市場経済」の導入を決定し、中国の経済は再び急激な経済発展を開始した。
経済が成長するにつれ、国民の貧富の格差や都市と地方農村の地域格差、汚職の蔓延、そして環境破壊などが目立つようになってきた。1991年に副首相に任命された朱鎔基は、改革開放の推進と経済の高成長を持続させるとともに、経済の過熱を冷却し物価上昇の抑制を図ることを目指した。
このため、インフレは沈静化し中国経済は高度成長を遂げた。
1997年7月には香港、1999年12月には澳門(マカオ)の中国への返還が実現し、列強の植民地化によって長らく分裂していた大陸が事実上初めて統一された。
(2)三大改革とWTO加盟
1998年3月に首相に就任した朱鎔基は、国有企業改革・金融改革・政府機構改革を、「2000年までに実現すべき三大改革」と位置づけた。とりわけ政府機構改革では国務院の省庁再編を行うとともに、汚職に対して厳しく臨んだ。
2001年に朱首相は、「国有企業改革の達成目標は基本的に実現し、金融改革の歩調は速まっている」と改革の成果を強調した。ただし、国有企業改革で多くの失業者を出したことなどについては批判も多かった。
2001年11月には中国のWTO(世界貿易機関)への加盟が実現し、外資の導入と世界経済のグローバリゼーション化の動きに適応した輸出の強化により、世界の製造業大国へと中国を変貌させる基礎を築いた。その結果、1990年から2004年にかけて、中国のGDPが平均約10%近く伸び、世界最高の経済成長率を記録した。
WTOへの加盟により、中国の民間企業は他国の企業と対等に競争を進めていく必要が生じた。このため2002年6月、国務院の国家経済貿易委員会、財政部、科学技術部、国家税務総局は「国家産業技術政策」を公表して、科学技術などの面から民間企業の支援を進めた。
その結果、中国の民間企業はさらなる発展を遂げ、世界の工場と言われるまでになった。
2. 江沢民時代の科学技術の特徴
(1)スローガン~科教興国戦略
江沢民時代の科学技術の特徴の一つ目は、江沢民総書記がスローガンとした科教興国戦略である。
科教興国とは、科学技術と教育を経済社会発展の重要な手段と位置づけ、科学技術と教育の振興により国家を繁栄に導くことである。
1993年7月、中国政府は、科学技術の進歩を促進し、科学技術の成果を実際の生産力に転化させ、科学技術を経済と社会発展の基礎とすることを目的として「中華人民共和国科学技術進歩法」を制定した。
1995年5月、中国共産党中央と国務院は「科学技術の進歩の加速について」を決定し、中国の近代化を実現するために科学技術の進歩を加速させなければならないとして、科教興国戦略を提唱した。直後に開かれた全国科学技術大会で江沢民総書記が演説し、科教興国戦略を強調した。
1995年11月、科教興国戦略の一つとして、「211工程」による大学の重点化政策が開始された。211工程は、国家計画委員会、国家教育委員会、財政部が共同で決定したもので、中国の高等教育を世界的な水準にまで高めることを目的として全国で百校の重点大学を選定し、これらの重点大学を集中的に整備するものである。
1998年5月、江沢民総書記が北京大学で演説し、大学への投資をさらに重点化し世界一流の大学を構築する「985工程」の実施を宣言した。
これらの政策は、北京大学や清華大学などを世界レベルの大学に押し上げたことで成果があった。
(2)研究開発資金の大幅な拡充
江沢民時代の科学技術の特徴の二つ目は、研究開発資金の大幅な拡充である。
1992年春の南巡講話以降、改革開放路線が再確認されて外資導入が再開されると、沿岸部を中心に様々な製造業が発展し、中国は世界の工場としての地位を確立していく。この経済の発展が科学技術投資を促進していった。
中国政府は、1997年3月に基礎研究の重点化プロジェクトである「973計画」を開始した。さらに1998年5月、「国家科学技術奨励条例」を制定し、研究機関および研究者の研究開発に対するインセンティブを奨励することとした。
科学技術への投資が増加し、1992年に198億元(4500億円)であったものが、2003年には1,540億元(2兆1600億円)と約8倍も増加している。
ただ、次表の通り2003年時点の米国の研究開発費は2,940億ドル(34兆1,000億円)、日本は16兆8,000億円であるので、これらの国々との差はまだかなり開いていた。
図表 中国、米国、日本の研究開発費比較
| 国名 | 1992年の研究開発費 | 2003年の研究開発費 | 伸び率 |
| 中国 | 198億元(4,500億円) | 1,540億元(2兆1,600億円) | 7.78倍 |
| 米国 | 1,660億ドル(21兆30億円) | 2,940億ドル(34兆1,000億円) | 1.77倍 |
| 日本 | 13兆9,000億円 | 16兆8,000億円 | 1.21倍 |
(3)海外に滞在する研究者の帰国奨励
(3)海外に滞在する研究者の帰国奨励
江沢民時代の科学技術の特徴の三つ目は、海外に滞在する研究者の帰国奨励である。
文革終了後に鄧小平が主導した欧米や日本への留学生の派遣政策により、多くの優れた研究者が外国に滞在して活躍していたが、これを中国国内に戻して活躍させる回帰政策(海亀政策)が開始された。
文革時代に国内で研究者の育成が困難であったこともあり、国内の有力大学や中国科学院などの研究機関でも、優れた研究指導者は少なかった。改革開放政策による経済の進展により国内の大学や研究機関での施設・装置の充実や待遇の改善と相まって、欧米や日本で成果を挙げつつあった研究者を呼び戻す絶好のタイミングであった。
中国科学院が開始した百人計画は、その先駆をなすものであった。
(4)朱鎔基改革の科学技術への影響
江沢民時代の科学技術の特徴の四つ目は、朱鎔基改革の科学技術への影響である。
国の科学研究機関において、組織の断片化、分散化、重複、過剰な人員配置、低効率などの問題が顕在化してきた。朱鎔基首相は三大改革の一環として、科学技術に関する企業や機構についても大胆な改革を実行していった。
1999年8月、中国共産党中央委員会と国務院は、「イノベーション、ハイテクの発展、産業化の実現に関する決定」を公表し、朱鎔基首相の改革路線に沿って科学技術改革を進めることを強調するとともに、改革により配置転換を余儀なくされた多くの科学技術人材の受け皿として、イノベーション強化とハイテク企業振興を提唱した。国有企業改革の一環で国有企業の傘下にあった研究機関の改編・企業化が進められた。
最初は、国家経済貿易委員会が管理する石炭局、機械局、冶金局、石油化学局など10の国家局所属の242の機関の改革が行われ、この成果を見つつ他の部局の研究機関でも改革が実施された。
WTOに加盟した中国の企業はグローバル化の荒波に直面するが、その際に共産党と政府は技術創新(イノベーション)を強化し、より高度な科学技術を駆使した産業への転換を図る産業技術政策を展開していった。
(5)知的財産保護政策の強化
江沢民時代の科学技術の特徴の五つ目は、知的財産保護政策の強化である。
中国は、1984年に工業所有権保護に関するパリ条約加入以来、特許制度などを整備してきたが、欧米などから見ると知的財産保護は十分でなかった。江沢民政権では、欧米や日本からの外資導入の拡大やWTOへの加入が重要なアジェンダとなったため、外国からの導入技術や研究者の知財権保護強化が進められた。
3. 江沢民時代の科学技術の成果
この時期は、21世紀に向けて中国の科学技術体制を整えた時代と考えられ、それほど華々しい成果は見えなかった。
その中で成果を挙げたのは、有人宇宙活動への足がかりである。ソ連崩壊後にロシアと交渉し、ソユーズ宇宙船の技術導入を経て中国版の宇宙船「神舟」の開発を進め、1999年11月に神舟1号の無人での打ち上げに成功している。その後、神舟2号から4号までを、実験動物やダミー人形などでの実験打ち上げを繰り返し、周到に有人での打ち上げを準備していった。
また、中国版のGPSシステム「北斗」の構築も進められ、2000年に2機、2003年に1機の航行測位衛星が打ち上げられて、実証実験が開始された。これは、米国、ロシアに続くものであった。
文革前や文革中の中国は、科学技術面でほぼ鎖国状態にあり、欧米などの国際的な論文誌に投稿することはまれであったが、この時代には投稿も徐々に増加し始めた。中国の科学論文数は次表の通り、1992年で世界の14位であり米国の約20分の1、日本の約5分の1であったが、2003年では世界6位で米国の約5分の1、日本の約6割にまで増加している。
図表 主要国の科学技術論文数の比較(単年、整数カウント法)
| 国名 | 1992年の論文数 | 順位 | 2004年の論文数 | 順位 |
| 中国 | 9,119 | 14 | 47,235 | 6 |
| 米国 | 191,913 | 1 | 248,276 | 1 |
| 日本 | 46,558 | 2 | 76,666 | 2 |
参考資料
・文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2019」https://www.nistep.go.jp/archives/41356