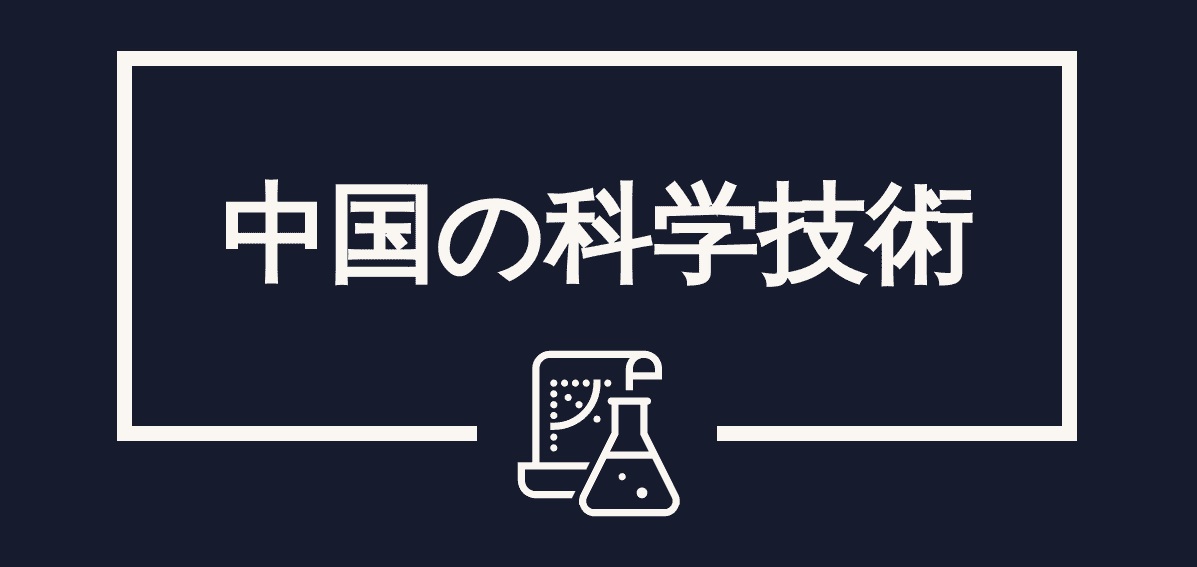はじめに
国家天文台は、北京市にある中国科学院の附属研究機関である。
最先端の天文観測機器を用いて、銀河宇宙論、恒星と宇宙の進化、太陽物理学、惑星科学などの研究を行っている。
国家天文台が形成された経緯から、北京を中心とした本部と4つの直属単位を有している。

1. 名称
○中国語表記:国家天文台
○日本語表記:国家天文台
○英語表記:National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences 略称 NAOC
2. 本部と4直属単位
国家天文台は2001年に現在の組織となったが、下記に述べる沿革により、北京を中心とした本部(总部)と4つの直属単位、具体的には雲南天文台(云南天文台)、南京天文光学技術研究所(南京天文光学技术研究所)、新疆天文台(新疆天文台)、長春人工衛星観測所(长春人造卫星观测站)から成り立っている。
国家天文台本部は、北京市朝陽区大屯路甲20号にある。北京市の中心である天安門から10キロメートルほど北にある。近くには、オリンピックのメイン会場となった北京国家体育場(通称、鳥の巣)があり、西に行くと中国農業大学を経て、清華大学や北京大学に達する。また、中国科学院の施設としては、生物物理研究所、微生物研究所などがある。

3. 沿革
国家天文台は、2001年に北京天文台、雲南天文台などの組織が統合再編されて成立した機関である。
(1)北京天文台
北京天文台は、国家天文台本部の前身であり、1958年に中国科学院傘下の研究機関として設置された。
北京天文台は、その後興隆(兴隆、河北省)、懐柔(怀柔、北京市郊外)、密雲(密云、北京市郊外)、沙河(河北省)、天津に天体観測基地を設けている。
(2)雲南天文台
雲南天文台(云南天文台)は、紫金山天文台(下記8.の特記事項参照)が日中戦争時に雲南省昆明に疎開していた際に設置された天文施設を前身としている。
辛亥革命後の混乱期を経て成立した国民政府時代に、中央研究院が南京を中心に科学技術振興を目指して設置され、その一つの研究機関として天文研究所が設置された。
中央研究院天文研究所は、南京市内の紫金山に60センチの反射望遠鏡など、当時としては近代的な設備を設置し、天文研究を進めた。
1937年に日中戦争が始まり、南京が同年末に占領されたため、中央研究院天文研究所は雲南省昆明に疎開し、雲南市内の風凰山に新たに天文台を建設した。この時期に天文研究所の所長として活躍したのが、中国近代天文学の基礎を築いた張鈺哲である。

日本の敗戦後、中央研究院天文研究所は南京に戻ったが、鳳凰山の天文施設はそのま天文研究所の研究点(工作站)として維持された。
1949年に新中国が建国されると、中央研究院天文研究所は中国科学院に接収され、同院の直属機関として紫金山天文台が設置された。その際に雲南にあった研究点は紫金山天文台昆明研究点(昆明工作站)となった。併せて、130ミリの屈折赤道儀望遠鏡も設置された。
1972年に、昆明研究点は紫金山天文台から独立し、雲南天文台として中国科学院の直属研究機関となった。
2001年に、雲南天文台は国立天文台に統合され、国立天文台の直属単位の一つとなった。

(3)南京天文光学技術研究所
南京天文光学技術研究所(南京天文光学技术研究所)の前身は、1958年に中国科学院直属の機関として南京に設置された南京天文計器工作所(南京天文仪器厂)である。
1991年に、名称が南京天文計器開発センター(南京天文仪器研制中心)に改称された。
2001年の国立天文台設置の際に、南京天文計器開発センターが改編されて南京天文光学技術研究所となり、国立天文台の直属単位の一つとなった。

(4)新疆天文台
新疆天文台の前身は、1957年に中国科学院直属の機関として新疆ウイグル自治区のウルムチ(乌鲁木齐)に設置された中国科学院ウルムチ人工衛星観測点(中国科学院乌鲁木齐人造卫星观测站)である。
1987年に、中国科学院ウルムチ天文点(中国科学院乌鲁木齐天文站)と改名され、2001年の国立天文台設置の際に国立天文台の直属単位の一つとなった。
2011年には、国立天文台の直属単位の位置づけのまま、新疆天文台と改名された。

(5)長春人工衛星観測点
長春人工衛星観測点(长春人造卫星观测站)は、1957年に吉林省長春に設置され、2001年の国立天文台設置の際に国立天文台の直属単位の一つとなった。

4. 組織の概要
(1)研究分野
国家天文台は、最先端の天文観測機器を用いて、銀河宇宙論、恒星と宇宙の進化、太陽物理学、惑星科学などの研究を行っている。
(2)研究組織
①国家級の研究室・実験室
国家天文台には、国家級の研究室・実験室がない。
②中国科学院級研究室・実験室
・中国科学院光学天文重点実験室(中国科学院光学天文重点实验室)
・中国科学院太陽活動重点実験室(中国科学院太阳活动重点实验室)
・中国科学院月・深宇宙探査重点実験室(中国科学院月球与深空探测重点实验室)
・中国科学院宇宙天文・技術重点実験室(中国科学院空间天文与技术重点实验室)
・中国科学院計算天体物理重点実験室(中国科学院计算天体物理重点实验室)
・中国科学院FAST重点実験室(中国科学院FAST重点实验室)
・中国科学院天文光学技術重点実験室(中国科学院天文光学技术重点实验室、南京天文光学技術研究所に設置)
・中国科学院天体構造・進化重点実験室(中国科学院天体结构与演化重点实验室、雲南天文台に設置)
・中国科学院電波天文重点実験室(中国科学院射电天文重点实验室、紫金山天文台が中心であるが新疆天文台も一部参画している)
③研究部
・光天文学
・電波天文学(射电天文)
・銀河宇宙論(星系宇宙学)
・太陽物理(太阳物理)
・宇宙科学(空间科学)
・月・深宇宙探査(月球与深空探测)
・応用天文学(应用天文)
④観測点(例示)
・河北省:興隆、密雲、懐柔
・天津市:武清
・雲南省:昆明鳳凰山、麗江高美谷、澄江伏仙湖
・新疆ウイグル自治区:南山、七台、カシュガル、烏拉台
・チベット自治区:阿里、楊巴井
・内モンゴル自治区:明安图
・吉林省:净月潭
・貴州省:平塘
・アルゼンチン:サンファン
(3)国家天文台本部の幹部
国家天文台本部の幹部は、中国共産党委員会(党委)書記、台長、副台長、党紀律委書記である。なお、四つの直属機関にもそれぞれ台長や党委書記などが置かれている。
①汪洪岩・党委書記
汪洪岩・国家天文台党委書記兼副台長は、1970年生まれで、1993年に北京にある中央民族大学で学士の学位を取得し、中国科学院では事務部門を中心に勤務してきた。2004年に中国科学院本部の弁公室秘書処処長となり、2009年弁公室副主任、2011年中国科学院物理研究所党委副書記兼副所長などを経て、2021年から国家天文台の党委書記兼副台長を務めている。
②劉継峰・台長
劉継峰(刘继峰)国家天文台台長兼党委副書記は、研究所のナンバーツゥである。劉継峰は、1973年に山東省で生まれ、1996年に北京大学天体物理学科で学士学位を、1999年に修士学位を、2005年に米国ミシガン大学で博士学位を、それぞれ取得した。その後、米国ハーバード・スミソニアン天体物理観測所で勤務し、2010年に百人計画に当選して中国科学院国家天文台の研究員となった。2018年に同天文台の副台長となり、2023年に台長兼党委副書記となった。専門分野は、天体と恒星のマルチバンド観測である。
5. 国家天文台の規模
(1)職員数
国家天文台(直轄の研究機関を含む)の2021年現在の職員総数は1,411名で、中国科学院の中では第8位に位置する(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。1,411名の内訳は、研究職員が1,183名(84%)、技術職員(中国語で工員)が102名(7%)、事務職員が126名(9%)である。
このうちそれぞれのHPの情報によれば、本部職員が約700名、雲南天文台職員が約300名、新疆天文台職員が約150名、長春人工衛星観測点職員が約70名であり、南京天文光学技術研究所研究員が約30名となっている。
(2)予算
国家天文台(直轄の研究機関を含む)の2021年予算額は15億3,812万元で、中国科学院の中では第11位に位置する(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。15億3,812万元の内訳は、政府の交付金が8億1,718万元(53%)、NSFCや研究プロジェクト資金が6億0,577万元(39%)、技術収入が7,890万元(5%)、試作品製作収入が551万元(1%)、その他が3,076万元(2%)となっている。
(3)研究生
国家天文台(直轄の研究機関を含む)の2021年現在の在所研究生総数は360名で、中国科学院の中で30位までのランキング内には入っていない(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。360名の内訳は、修士課程の学生が118名、博士課程の学生が242名である。
6. 研究開発力
(1)国家級実験室など
中国政府は、国内にある大学や研究所を世界レベルの研究室とする施策を講じている。この施策の中で最も重要と考えられる国家研究センターと国家重点実験室であり、中国科学院の多くの研究機関に設置されている(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。国家天文台は国家重点実験室を有していない。
(2)大型研究開発施設
中国科学院は、同院や他の研究機関の研究者の利用に供するため大型の研究開発施設を有している。大型共用施設は、専用研究施設、共用実験施設、公益科学技術施設の3つのカテゴリーがある(中国科学院内の設置状況詳細はこちら参照)。
国家天文台は、この大型共用施設・共用実験施設として「天体望遠鏡(LAMOST)」と「500メートル球面電波望遠鏡(FAST)」を設置・運営している。
①天体望遠鏡(LAMOST)
天体望遠鏡 LAMOST(The Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope:広視野多目標光ファイバー分光観測天体望遠鏡)は、北京の東北約120キロメートルに位置する河北省承徳市興隆県に設置されている。興隆県の中心部の海抜は約400メートルとかなり高地にあり、LAMOSTは興隆県の東部に位置する山の頂き(海抜約960メートル)にある。1993年にプロジェクトとして発足し、2001年に装置の製造建設がはじまり、2008年に完成した。
LAMOSTの特徴は、同時に収集できる天体の可視光スペクトル数である。視野角5度の範囲内で、4千個の恒星や銀河などの天体を同時観測できる仕組みになっている。湿度が低く空気中のチリなどの不純物が少ないため、観測に適している冬の夜であれば1晩で5回の観測が可能となり、2万個の天体データを収集できる。

②500メートル球面電波望遠鏡(FAST)
500メートル球面電波望遠鏡・FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope)は、中国南西部の貴州省平塘県にあり、4,600枚の三角形のパネルを組み合わせた固定球面鏡を有しており、直径は世界最大と言われる500メートルである。このFASTにより、天の川銀河やその他の銀河の観測や、パルサー(パルス状の可視光、電波、X線を発生する天体)の活動の観測ができるという。また、遠い銀河にある惑星などから生命の源となるアミノ酸が検出されるという期待もある。

(3)NSFC面上項目獲得額
国家自然科学基金委員会(NSFC)の一般プログラム(面上項目、general program)は、日本の科研費に近く主として基礎研究分野に配分されており、中国の研究者にとって大変有用である。国家天文台のNSFCの獲得資金額は、中国科学院の中で20位までのランキング内には入っていない(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。
7. 研究成果
(1)Nature Index
科学雑誌のNatureは、自然科学系のトップランクの学術誌に掲載された論文を研究機関別にカウントしたNature Indexを公表している。Nature Index2022によれば、国立天文台は論文数であるカウントで75、貢献度を考慮したシェアで14.16であり、中国科学院の中で20位までのランキング内には入っていない(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。
(2)SCI論文
上記のNature Indexはトップレベルの論文での比較であり、より多くの論文での比較も重要である。しかし、中国科学院は各研究所ごとの論文数比較を出来るだけ避け、中国科学院全体での比較を推奨している。このため、SCI論文などで研究所ごとの比較一覧はない。
ただ、研究所によっては自らがどの程度SCI論文を作成しているかを発表している。国家天文台(本部のみ)もその一つであり、2021 年に合計746件のSCI論文を発表している。
なお、1年間で746 件という数字を中国の主要大学のそれと比較すると、清華大学、北京大学、上海交通大学などが1年間で、SCI論文を2万~3万件前後発表している(詳細はこちら参照)。したがって中国の主要大学と比較すると、それほど大きなものではない。
(3)特許出願数
2021年の国家天文台の特許出願数であるが、本部と直属機関で別々に集計されいており、本部32件、新疆天文台20件、雲南天文台19件、南京天文光学技術研究所6件、長春人工衛星観測点1件となっている。これらを合計すると78件となるが、中国科学院内で20位までのランキング外である(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。
(4)成果の移転収入
2021年の研究所の研究成果の移転収入は、中国科学院内でランキング外である(他の研究所との比較の詳細はこちら参照)。
(5)両院院士数
中国の研究者にとって、中国科学院の院士あるいは中国工程院の院士となることは生涯をかけての夢となっている。2025年4月時点で国家天文台(直属単位を含む)に所属する両院の院士は10名であり、中国科学院内で第7位である(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。
○本部の中国科学院院士(7名):陈建生、欧阳自远、艾国祥、武向平、汪景琇、常进、赵刚
○雲南天文台の中国科学院院士(1名):韩占文
○南京天文光学技術研究所の中国科学院院士(2名):苏定强、崔向群
8. 特記事項
紫金山天文台と上海天文台は国家天文台と緊密な連携関係にあるが、それぞれ独立しており中国科学院直轄の研究機関である。
(1)紫金山天文台
紫金山天文台(Purple Mountain Observatory)の前身は、国民政府時代の1928年に中央研究院天文研究所として設置された。新中国建国後、中国科学院に接収されて、紫金山天文台となった。宇宙空間ダークマター、天体宇宙天文観測、南極天文観測、天体運行観測などを行っている。より詳しくはこちらを参照されたい。

(2)上海天文台
上海天文台(Shanghai Astronomical Observatory)の前身は、イエズス会が1872年に上海の徐家匯に設置した徐家匯天文台に遡る。1900年には上海の中心部から約30キロ離れた佘山の頂上に佘山天文台に設置された。新中国建国後、これらの施設は中国科学院に接収され紫金山天文台の支所となったが、1962年に独立して上海天文台となった。地球動力学、天体物理、天体運行科学、先進観測技術などの研究開発を行っている。より詳しくはこちらを参照されたい。

参考資料
・中国科学院統計年鑑2022 中国科学院発展企画局編
・中国科学院年鑑2022 中国科学院科学伝播局編
・国家天文台HP https://www.bao.ac.cn/
・雲南天文台HP https://ynao.cas.cn/jggk/jgjj/
・南京天文光学技術研究所 http://www.niaot.cas.cn/
・新疆天文台HP http://www.xao.ac.cn/
・長春人工衛星観測点 http://www.cho.ac.cn/
・中国科学院紫金山天文台 http://www.pmo.ac.cn/
・中国科学院上海天文台 http://www.shao.ac.cn/