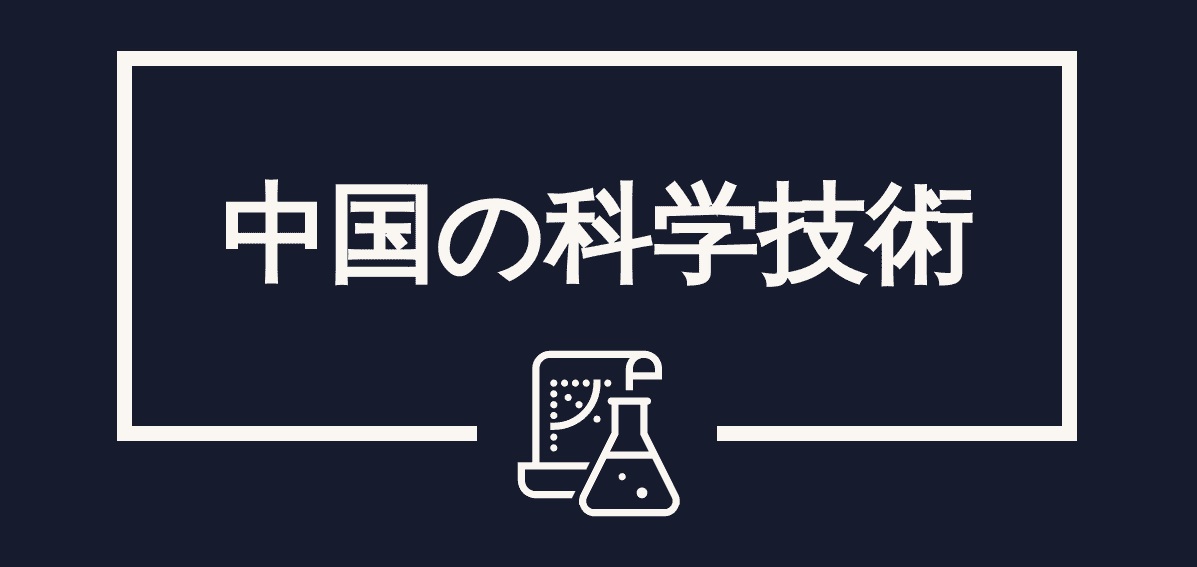1. 概要
「中国の宇宙開発~中国は米国やロシアにどの程度近づいたか~」は、2019年1月20日に、株式会社アドスリーより発行された(ISBN 978-4-904419-82-3)。
書籍の紹介文:2003年、米ソに次いで世界で3番目に有人飛行に成功して以来、中国の宇宙開発の発展は急激である。本書では宇宙開発について、ロケット開発、人工衛星の利用、宇宙科学などに分けて、それぞれの発展の歴史や中国での開発状況を述べ、米国、ロシア、欧州、日本と中国の技術力を比較した。そのうえで、中国の宇宙開発の特徴を記述した。
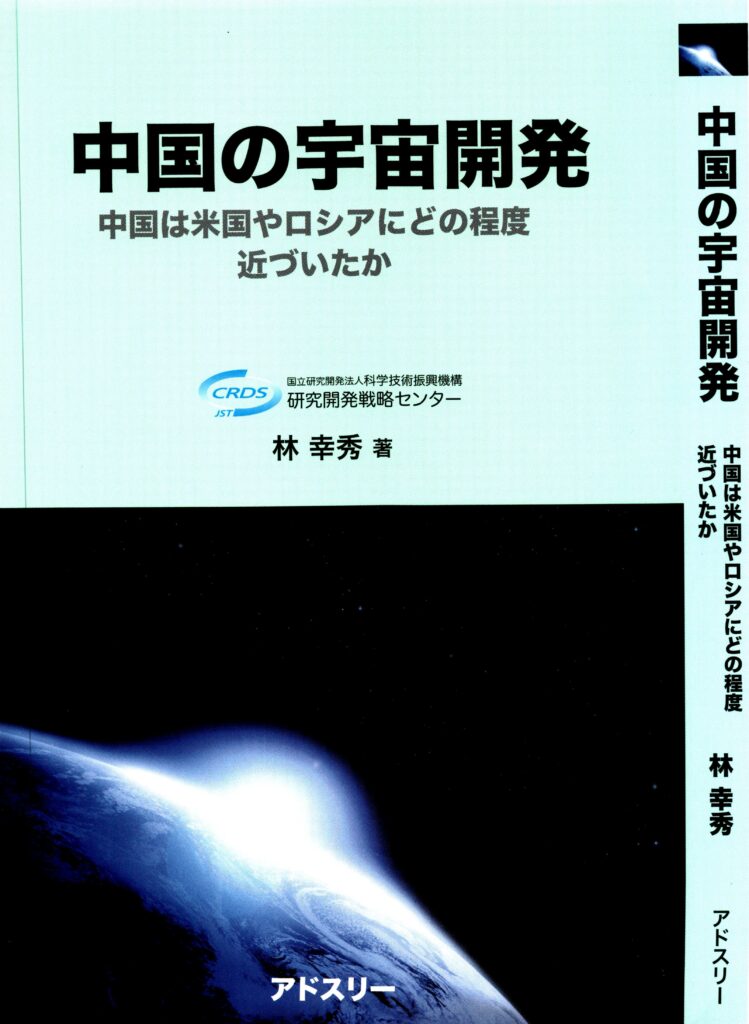
2. 各章の内容
本書は、既にアドスリーでは絶版となっている。そこで、書籍をデジタルスキャンしたデータを原稿と照らし合わせてワード化し、それをPDF化したものを記録として残し、興味のある読者に読んで貰うため、以下に掲載する。
はじめに
はじめにを読む
序章
序章を読む
第一章 中国の宇宙開発史概略
宇宙とは/新中国の建国と朝鮮戦争/両弾一星/ソ連からの援助とその中断/中国の宇宙開発の父銭学森と蒋英夫人/
両弾一星の完成/長征ロケットと各種人工衛星の開発/有人宇宙飛行計画「神舟」/独自の宇宙ステーション「天宮」の建設へ/月探査などの宇宙科学への挑戦/打ち上げの失敗/衛星破壊実験/
第一章を読む
第二章 宇宙輸送システム
1 ロケット開発の歴史
(1)ロケットの原理と種類/(2)人工衛星などの軌道/(3)原型は中国発の発明 /(4)近代におけるロケットの開発/(5)サターンV型ロケット/(6)ESAによるアリアンロケット開発/(7)スペースシャトル/(8)スペースX/
2 中国のロケット
(1)「長征」シリーズ/(2)将来計画/
3 打ち上げ射場
(1)選定条件/(2)各国の打ち上げ射場
4 中国の打ち上げ射場と着陸場
(1)地理的な位置/(2)酒泉衛星発射センター/(3)太原衛星発射センター/(4)西昌衛星発射センター/(5)中国文昌航天発射場/(6)四子王旗着陸場/
5 打ち上げ後の追跡管制
(1)中国西安衛星測控センター/(2)北京航天飛行控制センター/(3)中国衛星海上測控部/(4)データ中継衛星「天鏈」/
6 国際的な比較
(1)打ち上げ数および信頼性/(2)評価のまとめ/
第二章を読む
第三章 人工衛星バス技術
1 衛星バスの構成要素
(1)構体/(2)電力システム系 /(3)姿勢制御系/(4)推進系 /(5)コマンド・データ処理系/(6)熱制御系/
2 中国の衛星バスの種類
(1)静止通信衛星バス東方紅4型/(2)開発中の東方紅5型/(3)その他の衛星バス/
3 国際的な比較
(1)各国の静止衛星用の標準衛星バス /(2)評価のまとめ /
第三章を読む
第四章 通信放送
1 衛星通信放送の歴史
2 通信衛星の種類
3 中国の通信衛星開発
4 衛星通信放送技術の開発
5 中国の衛星通信放送会社
6 国際的な比較
第四章を読む
第五章 航行測位
1 衛星航行測位の歴史
(1)トランシットの開発/(2)GPSの開発/(3)GPSを用いたカーナビの開発/(4)民生用GPSの精度向上
2 各国の航行測位衛星
(1)米国 /(2)GNSSとRNSS/(3)ロシア/(4)EU/(5)日本/
3 中国の航行測位衛星
(1)中国の航行測位衛星システム〜北斗/(2) 北斗1号システム/(3) 北斗2号システム/(4)北斗3号システム 52
4 国際的な比較
第五章を読む
第六章 気象観測
1 衛星による気象観測の歴史
(1)気象衛星とは/(2)米国での開発/(3)WMOのネットワーク構想/(4)日本の気象衛星ひまわり/
2 中国の気象衛星
(1)風雲1号シリーズ /(2)風雲2号シリーズ/(3)風雲3号シリーズ/(4)風雲4号シリーズ/(5)国際貢献/
第六章を読む
第七章 地球観測
1 地球観測とリモートセンシング
(1)地球観測とは/(2)リモートセンシング/
2 中国の地球観測
(1)回収式衛星/(2)遥感シリーズ/(3)CBERSと資源シリーズ/(4)海洋シリーズ/(5)環境シリーズ /(6)高分シリーズ/(7)天絵シリーズ /(8)その他/
3 国際的な比較
第七章を読む
第八章 有人宇宙飛行
1 有人宇宙飛行の歴史
(1)ガガーリンによる世界初の宇宙飛行/(2)アポロ計画/(3)デタント/(4)サリュート/(5)スカイラブ/(6)スペースシャトルとスペースラブ/(7)ミール /(8)国際宇宙ステーション/
2 中国の有人宇宙飛行
(1)有人飛行計画の前段階/(2)有人宇宙船「神舟」の開発/(3)無人飛行での周到な準備/(4)楊利偉飛行士/(5)さらなる有人技術の習得
3 天宮1号
(1)実験機「天宮1号」と神舟8号の打ち上げ/(2)神舟9、10号と初の女性宇宙飛行士/(3)天宮1号の落下/
4 天宮2号
(1)天宮2号の打ち上げ/(2)神舟11号の打ち上げ/(3)無人補給船「天舟」の打ち上げ
5 「天宮」の建設〜将来計画
6 国際的な比較
第八章を読む
第九章 宇宙科学
1 宇宙科学の歴史
(1)天文学の歴史と宇宙科学/(2)月探査/(3)内太陽系探査/(4)外太陽系探査/(5)彗星探査/(6)小惑星探査 /
(7)科学衛星/(8)宇宙望遠鏡/
2 中国の天文学、宇宙探査の歴史
(1)中国の天文学の始まり/(2)偉大な天文学者・張衡の出現/(3)日本の暦にも影響を及ぼした郭守敬/
3 嫦娥計画など
(1)出遅れた宇宙科学/(2)探査計画1〜月軌道周回/(3)探査計画2〜探査機着陸/(4)探査計画3〜サンプルリターン /(5)着陸計画、滞在計画/(6)月探査以外の科学衛星/
4 国際的な比較
第九章を読む
第十章 中国における宇宙開発の担い手
1 政治行政体制
2 国務院
(1)工業・情報化部/(2)国家国防科技工業局/(3)国家航天/(4)中国科学院/(5)その他の国務院の機関/
3 人民解放軍
(1)中央軍事委員会と人民解放軍/(2)人民解放軍・戦略支援部隊/(3)航天系統部/(4)人民解放軍航天員大隊/
4 中国航天科技集団有限公司
(1)中国運載火箭技術研究院/(2)航天動力技術研究院/(3)中国空間技術研究院/(4)航天推進技術研究院/(5)上海航天技術研究院/(6)中国衛星通信集団有限公司/(7)中国長城工業集団有限公司/
5 中国航天科工集団有限公司
(1)中国航天科工信息技術研究院/(2)中国航天科工防御技術研究院/(3)中国航天科工飛行技術研究院/(4)中国航天科工動力技術研究院/
6 宇宙開発資金の国際比較
第十章を読む
第十一章 国際協力
1 国際連合での宇宙国際協力
2 宇宙関連の国際条約・協定
(1)宇宙条約/(2)宇宙救助返還協定/(3)宇宙損害責任条約/(4)宇宙物体登録条約/(5)月協定/
3 中国の宇宙国際協力
(1)基本的な立場/(2)二国間での協力/(3)一帯一路政策/(4)外国衛星の打ち上げ/(5)APSCOとAPRSAF
4 将来の国際協力の可能性
第十一章を読む
第十二章 国別宇宙技術力比較
1 直近の技術力比較
2 技術力比較の推移
3 2016年以降の主な進展
(1)各国の宇宙活動状況/(2)各国の主な宇宙開発成果/(3)2015年評価の補正/
4 各国の状況
(1)米国/(2)ロシア(旧ソ連)/(3)欧州(ESA)/(4)日本/(5)中国/
第十二章を読む
第十三章 中国の宇宙開発の特徴
1 強み
(1)豊富な資金/(2)圧倒的なマンパワー/(3)急激に拡大する宇宙関連市場/(4)着実なプロジェクトの進め方/
2 課題
(1)貧弱な宇宙科学活動/(2)オリジナリティに課題/
3 留意点
(1)軍が直接関与/(2)司令塔がない/
第十三章を読む
あとがき、参考文献等、著者紹介
3. 書籍全体
「中国の宇宙開発」を通して読む場合には、こちらを参照されたい。
4. 書籍の保存資料
「中国の宇宙開発」は、2019年1月20日に発行されたものであるが、その後絶版となっている。そこで、手元に残っている書籍をデジタルスキャンしPDFに変えて、閲覧・保存用に掲載した。なお、閲覧は可能であるが、著作権を考慮して印刷には透かしが入る。また、編集は不可である。
「中国の宇宙開発」のPDF(保存用)は、こちらを参照されたい。
なお、本書は、以下の通り国会図書館に収蔵されている。
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I029426431
参考資料
・JST・研究開発戦略センターHP 中国の宇宙開発 -中国は米国やロシアにどの程度近づいたか- https://www.jst.go.jp/crds/report/18BK01.html
・「G-TeC報告書 世界の宇宙技術力比較(2015年度)」 2016年5月
次のHP(JSTの研究開発戦略センターのサイト)からダウンロード可能である。
https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2016-CR-01.html
・「G-TeC報告書 世界の宇宙技術力比較(2013年)」 2014年3月
次のHP(JSTの研究開発戦略センターのサイト)からダウンロード可能である。
https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2013-CR-02.html
・「G-TeC報告書 世界の宇宙技術力比較」2011年11月
次のHP(JSTの研究開発戦略センターのサイト)からダウンロード可能である。https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2011-CR-02.html
・「科学技術大国中国」
・「中国科学院」