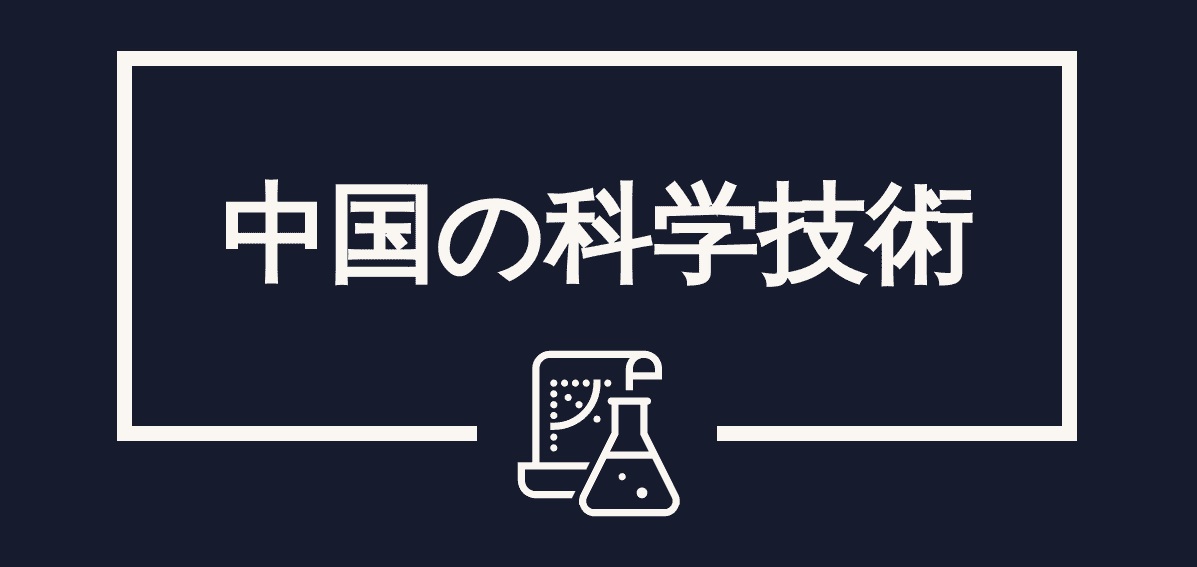はじめに
中国社会科学院(Chinese Academy of Social Sciences)は、国務院の直属事業単位の一つであり、人文社会科学分野における研究機関であり、顕著な功績を挙げた研究者の顕彰機関でもある。
国務院の直属事業単位(直属事业单位)とは、国務院に直属した独立組織であり、科学技術部のような組成部門(日本の各省に相当)ではないが、一定の行政的な権能を有する組織である。他に中国科学院、中国工程院などがある。

1. 名称
〇中国語:中国社会科学院 略称:中国社科院
〇日本語:中国社会科学院
〇英語:Chinese Academy of Social Sciences 略称:CASS
2. 所在地
中国社会科学院は、北京市東城区建国門内大街5号にあり、天安門から2キロメートルほど東に行ったところである。
3. 沿革
中国社会科学院は、元々中国科学院の一部が文化大革命後に分離独立してできた組織である。
(1)前史~中央研究院と北平研究院
中国科学院が設立されたのは第二次大戦後の中華人民共和国(新中国)の建国後であるが、母体となった組織は国民政府時代に設立された中央研究院と北平研究院である。
国民政府は1928年4月、国の最高研究機関として中央研究院を設立し、蔡元培を初代の院長とした。同研究院は傘下に自然科学、人文科学、社会科学の14の研究所を設置した。その中には、歴史語言、国文学、考古学、心理学、教育、社会科学の研究所があった。
さらに国民政府は、1929年9月、北平大学の研究機構を一部統合整理して北平研究院を創立した。同研究院の研究部門は気象、物理・化学、生物、人文地理、経済管理、文芸の6部門であった。
(2)中国科学院の設立~中央研究院と北平研究院の接収
1949年10月に中華人民共和国が建国され、中国科学院が設置された後、中国科学院はそれまでの中国の科学技術・学術研究の遺産ともいえる中央研究院と北平研究院の施設や人員の接収を実施し、新生中国のために科学技術・学術研究の基盤を確立していった。
1950年6月に中国科学院内に15の付属機関が設置されるが、この中に次の4つの社会、人文科学関連の研究所があった。
・近代史研究所(北京)
・考古研究所(北京)
・語言研究所(北京)
・社会研究所(南京、1952年に北京へ移転)
(3)哲学社会科学部の設置
1955年、中国科学院は学術分野ごとに「学部(Academic Divisions)」を設置し、そこに関連の研究者を集めて委員会を立ち上げて傘下の研究所の指導を行うこととした。
物理学数学化学部、生物学地学部、技術科学部、哲学社会科学部の4つの学部が置かれ、哲学社会科学部主任には中国科学院の院長であった郭沫若が兼務した。
(4)中国科学院から分離独立
文化大革命終了後の1977年5月、中国科学院の哲学社会科学部は中国科学院から分離独立し、中国社会科学院となり、初代院長には、政治家であり文人であった胡喬木が就任した。
独立した時点では、哲学、世界宗教、考古、歴史、近代史、世界歴史、文学、外国文学、言語、法学、民族、世界経済、情報資料の14の研究単位が存在し、スタッフ総数は2,200名を数えた。
(5)傘下の研究機関を拡大
その後、地域研究などを中心として研究機関が新たに設置され、現在、傘下に31の研究所と45の研究センターを有していて、スタッフ総数は4,200名を超えている。
4. 組織
(1)指導者と本部部局
中国社会科学院の指導部は、院長(国務院の部長(国務大臣)クラス)である。2025年6月現在の院長は、歴史学者で中国歴史研究院院長の高翔である。
本部の部局として、科研局、人事教育局、国際協力局、財務基礎建設管理局などがある。
(2)直轄組織
中国社会科学院は、すでに述べたように傘下に31の研究所と45の研究センターを有している。これらはそれぞれ文学・哲学、経済学、社会・政治・法学、歴史学、国際問題研究、マルクス主義研究の6つの学部のいずれかに属している。
5.学部委員
中国科学院時代の1955年に、学部委員制度が設置され、社会人文科学関連でも哲学社会科学部が設置されて、中国国内の主要な科学者が学部委員に任命された。
1977年に、中国社会科学院が中国科学院から分離独立した際に、この学部委員制度も引き継がれた。
1994年1月、中国科学院は学部委員を「中国科学院院士」に改称したが、中国社会科学院は中国社会科学院学部委員の名称を変更しなかった。
中国社会科学院は現在も、学部委員の呼称を継続して使用しており、通常の学部委員と80歳以上の栄誉学部委員をおいている。中国社会科学院にも院士制度を導入すべきとの主張もあるが、現在は検討中となっている。
参考資料
・中国社会科学院HP http://www.cass.cn/
・維基百科HP 中国社会科学院